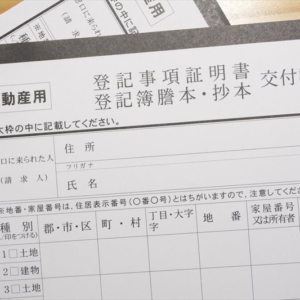不動産投資の個人と法人の違い、法人化のタイミング、節税効果を知る
不動産投資に取り組むにあたり、どの程度の規模になったら法人化を検討するとよいのでしょうか?
今回は、法人化のタイミングを検討の材料として、個人と法人の税率の違いや制度の違い、融資対策上の違いなどについてお伝えしていきます。
この記事の目次
不動産投資の個人と法人にはどんな違いがある?
まずは、不動産投資を個人と法人で取り組むのは、どのような違いがあるのか理解しておきましょう。
税制の違いがある
個人の場合は所得税が課され、法人の場合は法人税が課されます。確定申告の際、個人の場合、不動産保有時の家賃収入は不動産所得として計上し、不動産売却時の売却益は譲渡所得として計上するため、売却で損失が発生したとしても、原則として不動産所得と譲渡所得双方の損益通算(損失を利益で相殺すること)はできません。
一方、法人の場合は個人における不動産所得も譲渡所得も所得として扱うため、確定申告で売却益と所得の損益通算ができます。そのため、別の事業で出た黒字を不動産所得の赤字で相殺することが可能であり、全体の課税所得を減らすことが可能です。
関連ページ:家賃収入の所得税はどのくらいかかるのか?税金の計算方法を説明
家賃収入でも経費計上ができる!?
融資対策上での違い
一般的に、個人の不動産投資では、物件の収益性や担保評価と個人の信用力が重視されますが、法人の場合は業績が重視され、金融機関は決算書を詳細に見るはずです。
そのため審査前に、自己資金の多さや返済原資(主に当期利益)の豊富さをアピールできるような内容に仕上げておくと融資にプラスに働くでしょう。
個人と法人でかかる税率の違い

ここでは、個人の場合と法人の場合とでかかる税率の違いを見ていきましょう。なお、不動産投資では、主に不動産保有時と不動産売却時の税金を考える必要があります。
前述の通り、個人の場合は不動産保有時の収入は不動産所得として計上され、不動産売却時の収入は不動産の譲渡所得として計上されます。不動産所得は総合課税のため、累進課税で住民税(10%)と合わせると最大55%の税率となります。
一方、不動産の譲渡所得は分離課税で、短期譲渡所得(所有期間5年以下)のときに住民税と合わせて約39%、長期譲渡所得のときに住民税と合わせて約20%の税率となっています。
これに対し、法人の場合、不動産保有時・不動産売却時どちらの収入も法人税として計算できるため、その税率は最大で約37%です。
単純に数字だけを見ると、収入が多い場合は法人がお得で、所有期間5年超の不動産の売却では個人の方が有利となります。
個人(所得税と住民税)の税率と控除額
総合課税に関する個人の所得税と住民税の税率・控除額は以下の通りです。
課税所得金額195万円以下の場合…所得税+住民税15%、控除額0円
195万円超~330万円以下の場合…所得税+住民税20%、控除額97,500円
330万円超~695万円以下の場合…所得税+住民税30%、控除額427,500円
695万円超~900万円以下の場合…所得税+住民税33%、控除額636,000円
900万円超~1,800万円以下の場合…所得税+住民税43%、控除額1,536,000円
1,800万円超~4,000万円以下の場合…所得税+住民税50%、控除額2,796,000円
4,000万円超の場合…所得税+住民税55%、控除額4,796,000円
また、不動産の譲渡所得の税率 は以下の通りです。
長期譲渡所得(所有期間5年超)の場合…所得税+住民税20.315%
短期譲渡所得(所有期間5年以下)の場合…所得税+住民税39.63%
法人(法人税)の税率
一方、法人税の税率は以下の通りです。
課税所得金額400万円以下の場合…15%
400万円~800万円以下の場合…15%
800万円超の場合…23.2%
上記を見比べてみると分かる通り、課税所得が900万円を超えると所得税+住民税の43%より、法人税の36.81%のほうが税率は低くなります。そのため、所得が増えて「課税所得が900万円超」になったら、法人化を検討する1つの目安とするとよいでしょう。
ただし、不動産の売却を考えているのであれば、個人は所有期間5年超で20.315%の税率で済ませられることや、法人は家賃収入と不動産の売却益を損益通算できることなどがあるため、実際には総合的に判断する必要があります。
個人と法人の損失繰越期間の違い
個人と法人とでは、損失が出たときの繰越期間に違いがあることも知っておきましょう。
個人は最長3年
個人の場合、青色申告していることが条件となりますが、損失を3年まで繰り越すことができます。
例えば、ある年に2,000万円の損失を出した場合で、翌年に500万円の利益を出せば、その利益分については非課税とすることができ、残り1,500万円の損失をさらに翌年に繰り越すことが可能です。
法人は最長9年
一方、法人の場合は最長9年まで損失を繰り越すことができます。
ある年に大赤字を出してしまった、もしくは戦略的に大きな赤字とした場合でも、9年先まで損失を繰り越せるので、9年の間に黒字化できるとかなりの恩恵を受けることが可能です。なお、法人の場合でも、損失繰越は青色申告していることが条件となります。
個人と法人の減価償却の違い
減価償却とは、経過年数によって減少する建物や付帯設備などの価値の目減り分を、定められた期間で経費として計上することです。個人と法人とでは、この減価償却にも違いがあります。
個人は強制償却
個人の減価償却は、税法に定められた償却費が強制的に必要経費に算入されるため、「強制償却」と呼ばれています。そのため、たとえ誤って償却費を少なく計上してしまった場合でも、更生の請求対象となります。
法人は任意償却
一方、法人の減価償却は、税法で定められた限度額の範囲内で損金処理した金額が計上され、過少な償却でも容認されます。また、過少に申告されて残った部分は、次年度以降に償却することが可能です。
このように、法人の場合は限度額の範囲内であれば償却費を調整して計上してもよい、といった扱いになります。このことから、法人の減価償却は「任意償却」と呼ばれています。
法人の方が融資対策上プラスとなりやすい
なぜ、法人のほうが融資対策上プラスとなりやすいのか、ある年度の利益が200万円、減価償却費が300万円の場合を例として比べてみましょう。
この場合、個人の強制償却だと300万円全額を計上する必要がありますが、法人の任意償却であれば300万円を上限とし、いくらでも計上が可能です。減価償却費を0円として300万円の利益とすることも、減価償却費を300万円計上して100万円の赤字とすることもできます。
納 税額から見ると最終利益は少ないほうがよいのですが、融資審査から見ると利益は大きいほうがよいのが一般的です。そのため、合法的に利益を調整できる任意償却は融資対策上プラスとなりやすいのですが、その反面、利益を調整することで金融機関から決算書の操作を行っていると判断され、マイナス評価を受けてしまうリスクもあります。
不動産投資で法人化する規模とは?
不動産投資で法人化する規模は、どの程度を考えるとよいのでしょうか?
法人のほうが税率が低くなる規模で法人化する
まず、1つ目の判断基準として考えられるのは、「法人のほうが税率が低くなる規模で法人化する」ということです。
前述で個人と法人の税率を比べると、課税所得が900万円を超えると法人税のほうが低くなることが分かりました。したがって、課税所得が900万円を超えたときが法人化を検討するタイミングとなるでしょう。
収支に関係なく最初から法人化するのもおすすめ
収支に関係なく、最初から法人化するのも1つの方法です。法人には、税率の違いだけでなく、前述のように「9年間の損失繰越」や「減価償却費の任意償却」といったメリットがあります。
特に「いずれは法人化したい」と考えている方は、最初から法人化してしまってもよいでしょう。もし、すでに個人経営を行っている方が法人化する場合、所有している賃貸物件の名義変更手続きが必要となり、その際には不動産取得税や登録免許税などのコストがかかってしまいます。しかし最初から法人化することで、こういった手続きの手間やコストを抑えることができます。
法人化にはデメリットも…
ここまで法人化のメリットをお伝えしてきましたが、法人化にはデメリットがあることも知っておく必要があります。
まず、法人化するには定款認証料と登録免許税を負担する必要があり、株式会社の場合は最低でも20万円程度の初期費用 を支払わなければいけません。また、経理処理が複雑になるため、税理士に依頼する費用が発生することもデメリットと言えるでしょう。
さらに、個人事業主には65万円の青色申告特別控除が認められていますが、法人にはその控除がありません。そのほかにもデメリットとして、すでに個人経営を行っている方が途中から法人化する場合には、物件を法人名義に変更する手間や不動産取得税・登録免許税などのコストがかかってしまうことも挙げられます。
法人化のこうしたデメリットについて、しっかり理解したうえで法人化するかどうかを決めるとよいでしょう。
法人化を検討する際はメリット・デメリットの理解が大切
不動産投資に取り組むにあたって、どのくらいの経営規模やタイミングで法人化すればいいのかは悩むところでしょう。一般的には、個人事業主より法人化したほうが税率が低くなるタイミングで検討するのが合理的です。
ただし、法人化のメリットだけでなくデメリットも把握したうえで、比較検討することをおすすめします。
※写真はイメージです
※本記事は、2019年4月以前時点の情報をもとに執筆しています。 マーケットの変化や、法律・制度の変更により状況が異なる場合があります
※記事中では一般的な事例や試算を取り上げています。個別の案件については、お気軽にお問い合わせください。