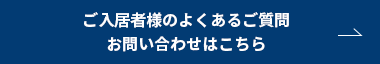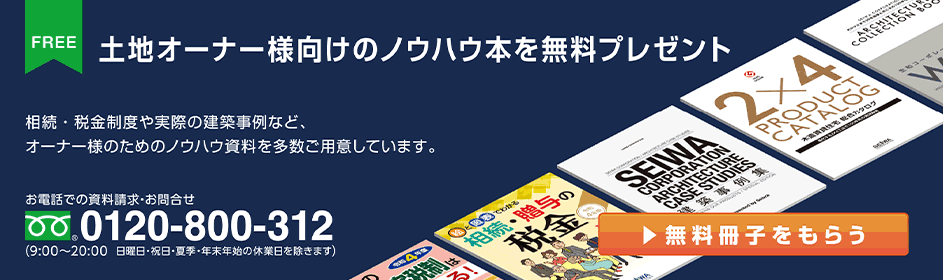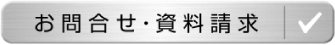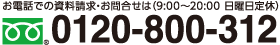相続財産と言われるもののなかには、預貯金をはじめ不動産や有価証券などの「プラス財産」だけではなく、借入金や未納の税金などの「マイナス財産」もあります。それらを相続する際には、プラスであれば相応の税金「相続税」を支払う事を求められます。良かれと思って子孫に遺した遺産があっても、この「相続税」を支払うことが負担になってしまう場合もあり得ます。そのため、土地を持っている人の中には相続税対策を目的として積極的に土地活用する人が多く存在します。では、なぜ土地活用が相続税対策につながるのでしょうか?
この記事の目次
相続税の仕組みについて
まず、基本的な相続税の仕組みについて説明します。相続税は、「相続財産」が「基礎控除」を超えた場合にかかります。そして、基礎控除を超えた分の相続財産を「課税遺産総額」と呼びます。この課税遺産総額を、各相続人が法定相続分通りに取得したと仮定して「相続税の総額」を計算します。その後、各相続人が実際に相続した割合に応じて相続税の総額を按分し負担する、というのが相続税のおおまかな仕組みです。
相続税は所得税などと同様に、課税対象の金額が大きくなるほど税率も上がるという累進課税方式となっています。このシステムによって、プラス財産が多ければ多いほど相続税の額が跳ね上がってしまいます。そのため、相続した財産の額が多い人ほど、相続税対策が必要と言われるのです。
土地活用一筋54年。累計着工戸数120,000戸超の実績。
冊子をプレゼント
アパートを建てると「貸家建付地」とされ20%の減税につながる
昔から「アパートを建てれば相続税対策になる」という事をよく言われてきていますが、なぜアパートやマンションなどの賃貸住宅を建設することが、相続税対策につながるのでしょうか?その理由としては、相続税の計算における「相続税評価額」は土地の利用形態によって変わるため、上手に土地活用をすることで意識的に節税をする事が可能だからです。例えばアパートやマンションを建てると、その土地の評価額は「貸家建付地」とされ、20%の評価減となります。さらに建物の相続税評価額も、地域ごとに定められている「借家権割合」に応じて減額されます。
ただし、例えば「親(被相続人)の名義」でアパートやマンションを建築した場合、建物の名義はあくまでも親(被相続人)なので、不動産収入は親のものとなります。そのため、不動産収入として現金資産が増え続け、結果としては期待したほどの節税効果が得られない場合があるので注意が必要です。
土地活用一筋54年。累計着工戸数120,000戸超の実績。
冊子をプレゼント
アパートを建てると「貸家建付地」とされ20%の減税につながる
まず、基本的な相続税の仕組みについて説明します。相続税は、「相続財産」が「基礎控除」を超えた場合にかかります。そして、基礎控除を超えた分の相続財産を「課税遺産総額」と呼びます。この課税遺産総額を、各相続人が法定相続分通りに取得したと仮定して「相続税の総額」を計算します。その後、各相続人が実際に相続した割合に応じて相続税の総額を按分し負担する、というのが相続税のおおまかな仕組みです。
相続税は所得税などと同様に、課税対象の金額が大きくなるほど税率も上がるという累進課税方式となっています。このシステムによって、プラス財産が多ければ多いほど相続税の額が跳ね上がってしまいます。そのため、相続した財産の額が多い人ほど、相続税対策が必要と言われるのです。
子供(相続人)名義のアパートやマンションを建設するのがおすすめ
その一方で、不動産収入を子供の所得にできるケースもあります。例えば、土地の名義は親のままにしておいて、子供名義のアパートやマンションを建てるという方法が効果的とされています。この場合、土地については貸家建付評価は受けられず、更地評価のままとなります。しかし、不動産収入が子供の所得となるので、資産形成や将来の相続税納税の財源として役に立ちます。また、最初は親名義で登記していても、後から子供へと名義変更する事も可能です。ただし、単純に不動産の名義を親から子供へ変更する場合は「贈与」となり、「贈与税」がかかってしまうため注意が必要です。節税目的で土地・建物の名義変更等を行うことは、専門的な内容となるため、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
今回ご紹介した手法はあくまで基礎的な内容となっているため、この記事に書かれていない細かな制約が数多くありますし、場合によってはアパートやマンションを建設しないほうが良いこともあります。まずは家族内でよく話し合い、専門家に相談した上で、どのケースが自分達に向いているか検討し、計画的な節税対策を実行してください。
関連ページ:土地の相続税評価額の計算方法は?
よくあるご質問
- 土地活用・不動産経営は初心者なのですが、どのように相談をおこなえばよいでしょうか?
- 弊社HPの電話もしくはお問い合わせフォーム・資料請求フォームから、お気軽にお問い合わせください。ご要望に応じて、オンライン面談・電話・メール等での対応が可能です。
- 生和コーポレーションの土地活用・不動産経営には、どのような特徴があるのですか?
- 4大都市圏での営業に特化し、土地活用一筋50年を超えております。マンション・アパートの累計着工戸数は100,000戸を超え、都市部に強い生和だからこそ、サブリース・一括借上げの入居率98%台を実現しています。
- お問い合わせ後の流れはどのようになっているのですか?
- お問い合わせ頂いた電話番号もしくはメールアドレスに担当がご連絡致します。
お客様のご相談内容に応じて、経験・知識が豊富な担当が対応致します。
他の「失敗しない土地活用」の記事を見る
-
 土地活用にはさまざまな方法があります。少子高齢化が進む現在は、将来のニーズを考え、土地活用の選択肢の一つとして「医療施設」を検討するとよいでしょう。 医療施設による土地活用は地域に貢献できるうえ、収益…
土地活用にはさまざまな方法があります。少子高齢化が進む現在は、将来のニーズを考え、土地活用の選択肢の一つとして「医療施設」を検討するとよいでしょう。 医療施設による土地活用は地域に貢献できるうえ、収益… -
 世の中にはさまざまな土地活用法があり、そのうちの一つが「商業施設」の経営です。 商業施設は立地次第で大きな収益が期待でき、地域活性化にもつながる土地活用法です。しかし、どのような土地が向いているのか、…
世の中にはさまざまな土地活用法があり、そのうちの一つが「商業施設」の経営です。 商業施設は立地次第で大きな収益が期待でき、地域活性化にもつながる土地活用法です。しかし、どのような土地が向いているのか、… -
 超高齢化社会に向かうと予想される日本では、社会貢献もできて安定収入も見込める土地活用方法として、介護施設の経営に注目が集まっています。 特に、広大な土地をお持ちのオーナー様は、土地の広さを活かして介護…
超高齢化社会に向かうと予想される日本では、社会貢献もできて安定収入も見込める土地活用方法として、介護施設の経営に注目が集まっています。 特に、広大な土地をお持ちのオーナー様は、土地の広さを活かして介護… -
 賃貸物件の経営方式には、おもに自主管理・管理委託方式・一括借上げ(サブリース)の3種類があります。この3種類のなかでも、不動産経営に興味を持っている方の間で近年浸透しつつあるのが、一括借上げ(サブリー…
賃貸物件の経営方式には、おもに自主管理・管理委託方式・一括借上げ(サブリース)の3種類があります。この3種類のなかでも、不動産経営に興味を持っている方の間で近年浸透しつつあるのが、一括借上げ(サブリー… -
 所有している土地を「有効的に土地活用すべきか」、それとも「売却すべきか」のどちらかでお悩みのオーナー様も多いかと思います。 また、売却をお考えでも、本当にそれが最善の判断なのか疑問に感じる方も多いでし…
所有している土地を「有効的に土地活用すべきか」、それとも「売却すべきか」のどちらかでお悩みのオーナー様も多いかと思います。 また、売却をお考えでも、本当にそれが最善の判断なのか疑問に感じる方も多いでし…
他の土地相続に関する情報を見る
-
 土地相続の際の手続きは、誰にでも起こりうる身近な法手続きのひとつです。しかし、土地相続の具体的な流れやかかる税金、必要書類などの詳しい知識を持っている人は、実際には少ないのではないでしょうか。そこで今…
土地相続の際の手続きは、誰にでも起こりうる身近な法手続きのひとつです。しかし、土地相続の具体的な流れやかかる税金、必要書類などの詳しい知識を持っている人は、実際には少ないのではないでしょうか。そこで今… -
 相続とは、ある人が亡くなったときに、その人が持っていた全ての財産を、その人の配偶者や子など一定の人が引き継ぐことをいいます。亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ一定の人を「相続人」、亡くなった人…
相続とは、ある人が亡くなったときに、その人が持っていた全ての財産を、その人の配偶者や子など一定の人が引き継ぐことをいいます。亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ一定の人を「相続人」、亡くなった人… -
 親や祖父母から不動産を相続した際には、相続手続きはもちろん、相続登記を行うことが大切です。 ここでは、不動産の相続手続きの進め方および相続登記方法について、具体的な流れと方法、注意点をまとめました。不…
親や祖父母から不動産を相続した際には、相続手続きはもちろん、相続登記を行うことが大切です。 ここでは、不動産の相続手続きの進め方および相続登記方法について、具体的な流れと方法、注意点をまとめました。不… -
 家族が亡くなった場合などで土地の相続をした人には、土地所有者の名義変更登記が必要になります。 ここでは、土地の相続登記が必要な理由や、手続きの流れと費用、そして手続きの注意点などについてご紹介します。…
家族が亡くなった場合などで土地の相続をした人には、土地所有者の名義変更登記が必要になります。 ここでは、土地の相続登記が必要な理由や、手続きの流れと費用、そして手続きの注意点などについてご紹介します。… -
 土地を相続することが決まった後、相続の話し合いが済んだだけでは土地の名義変更がなされていないことをご存知でしょうか。 実は、こうした相続財産の名義変更については義務ではありません。そのため、相続がなさ…
土地を相続することが決まった後、相続の話し合いが済んだだけでは土地の名義変更がなされていないことをご存知でしょうか。 実は、こうした相続財産の名義変更については義務ではありません。そのため、相続がなさ… -
 相続の際には、相続税が課税されます。税金は当然現金で支払う必要がありますが、なんらかの事情で相続税を払えないケースがあるようです。 そのようなケースは、どういった理由で発生するのか、いくつかの事例をも…
相続の際には、相続税が課税されます。税金は当然現金で支払う必要がありますが、なんらかの事情で相続税を払えないケースがあるようです。 そのようなケースは、どういった理由で発生するのか、いくつかの事例をも… -
 「相続税の支払いのために、先祖代々所有してきた土地を売却した」といったエピソードを聞かれたことのある方はいるのではないでしょうか。 また、将来的な不動産相続時に発生する相続税に関して、不安をお持ちの方…
「相続税の支払いのために、先祖代々所有してきた土地を売却した」といったエピソードを聞かれたことのある方はいるのではないでしょうか。 また、将来的な不動産相続時に発生する相続税に関して、不安をお持ちの方… -
 将来、土地を相続する予定のある方は、その際の相続税に関して何か対策されていらっしゃいますか? 相続税は場合によって、納税のために相続財産の売却まで必要になる深刻な事態を招くため、対策はしっかりとってお…
将来、土地を相続する予定のある方は、その際の相続税に関して何か対策されていらっしゃいますか? 相続税は場合によって、納税のために相続財産の売却まで必要になる深刻な事態を招くため、対策はしっかりとってお… -
 土地にかかる相続税の仕組みをご存知でしょうか。相続税対策を怠ると、相続税を支払うために資産を売却せざるを得ないなどの事態が発生する可能性もあるでしょう。 今回は、土地を相続した場合にかかる税金の内容、…
土地にかかる相続税の仕組みをご存知でしょうか。相続税対策を怠ると、相続税を支払うために資産を売却せざるを得ないなどの事態が発生する可能性もあるでしょう。 今回は、土地を相続した場合にかかる税金の内容、…