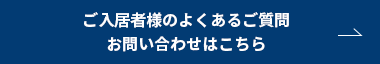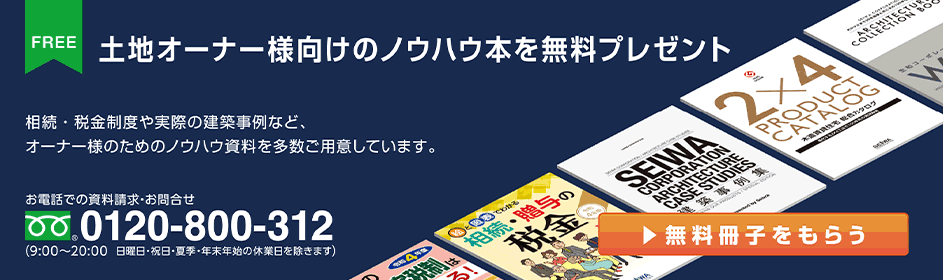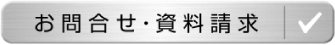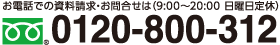この記事の目次
軽量鉄骨造とはどういう構造?

軽量鉄骨造とは、梁や柱などの骨組みに鉄骨を使用している工法のことです。
プレハブ工法によることが一般的で、事前に工場で製造された部材を現場で組み立てる方法で建築されます。
現場での手間を削減できることから比較的低コストで建築が可能で、戸建住宅やアパート、商業施設、倉庫など多様な用途で利用されています。
重量鉄骨造との違い
鉄骨造には、「軽量鉄骨造」と「重量鉄骨造」の2つの種類があります。
鋼材の厚さが6mm未満の鉄骨造を軽量鉄骨と呼び、鋼材の厚さが6mm以上の鉄骨造を重量鉄骨と呼ぶことが一般的です。
重量鉄骨造は、高層ビルやマンションなど、より強度を必要とする建物で使用される工法です。
ただし、これらの区別は建築基準法などで明確にされているものではなく、建築業界の中で区別する際に一般的な基準とされているものです。
軽量鉄骨造の法定耐用年数は?
法定耐用年数とは、減価償却手続きの対象となる資産を、法律で定められた期間にわたって費用として計上していくための基準です。
減価償却とは、建物や機械装置、車両など、時間の経過とともに価値が減少していく資産の取得原価を、それらを利用した会計期間の費用として配分する手続きです。
この法定耐用年数というのは、減価償却費を計算するために税法上定められた手続きのための期間ですので、実際に使用可能な耐用年数を表しているわけではありません。
法定耐用年数は建物の構造や用途によって一律に定められており、事業用建物の耐用年数を示すと、以下の表のようになります。
| 建物の構造 | 法定耐用年数 |
|---|---|
| 木モルタル造 | 20年 |
| 木造 | 22年 |
| 鉄骨造(3mm以下) | 19年 |
| 鉄骨造(3mm超4mm以下) | 27年 |
| 鉄骨造(4mm超) | 34年 |
| 鉄筋コンクリート造 | 47年 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 47年 |
国税庁:主な減価償却資産の耐用年数表
軽量鉄骨造の法定耐用年数は鋼材の厚さによって異なります。
大手の建築会社では、減価償却費の計上期間を27年間として計算している例が多いことから、3mm超4mm以下の鋼材を使用しているケースが多いです。
しかし、正確な耐用年数を調べるには、建築を依頼した建築会社に確認することが必要となります。
関連リンク:RC造(鉄筋コンクリート造)・S造(鉄骨造)・W造(木造)・SRC造(鉄筋鉄骨コンクリート造)の違いとは?
物理的耐用年数と経済的耐用年数について
耐用年数は、先ほど説明した法定耐用年数以外にも、物理的な耐久性を重視するか、経済的な利用価値に着目するかによって、
- 物理的耐用年数
- 経済的耐用年数
に分類することができます。
以下で、これらの違いについて解説します。
軽量鉄骨造のマンション・アパートの物理的耐用年数
物理的耐用年数とは、その建物を現実に使用可能な年数のことですが、法定耐用年数と比較すると長くなるのが通常です。
建物の構造や建材、設備などの耐久性の違いが物理的耐用年数に大きな影響を与えます。
また、建物の使用方法や周辺の環境などの条件によってもこの物理的耐用年数は大きく差が生じます。軽量鉄骨造の物理的耐用年数は、50~60年ほどが一般的です。
軽量鉄骨造のアパートについては、想定する物理的耐用年数がRC造等と比較して短いため外観等の劣化が早く、外壁材や建材、設備について比較的早期の修繕やリフォーム等のメンテナンスが必要となります。
軽量鉄骨造のマンション・アパートの経済的耐用年数
経済的耐用年数とは、建物の構造や資材、用途など物理的な減価をもたらす要因だけではなく、技術革新などによって生じる機能的な価値の減少や陳腐化によって、市場のニーズから取り残されるリスクなども加味した耐用年数を意味します。
物理的耐用年数には問題ないとしても、古い設備等をそのまま利用し続けることで相対的に建物の魅力が減少し、価格競争力が落ちることで家賃がとれにくくなる点(経済的価値の下落)に注意が必要です。
したがって、耐震化やリフォームなどを適時に行い、建物の機能的な減価を補うことができれば、経済的耐用年数は延びると考えられるでしょう。
減価償却費の計算方法
次に減価償却費の計算方法を解説します。
新築か中古か、また中古の場合は法定耐用年数が残っているか否かで計算方法が異なりますので、それぞれに分けて説明します。
平成19年3月31日以前に取得した場合には定額法と定率法の選択適用が認められていましたが、平成19年4月1日以後に取得した場合には、減価償却費の計算方法は定額法のみとされましたので、ここでは定額法の計算方法を説明します。
【平成19年4月1日以後に新築で取得した場合】
償却率とは、耐用年数に応じた減価償却費を計算するために使用される比率で、以下に記載する国税庁の「減価償却資産の償却率等表」から調べることができます。
【平成19年4月1日以後に中古で取得した場合】
中古の場合は法定耐用年数が残っているか否かで計算式が変わります。
(法定耐用年数が残っている場合)
減価償却費=建物の取得原価×中古物件の耐用年数の償却率×経過月数÷12
(法定耐用年数が残っていない場合)
減価償却費=建物の取得原価×中古物件の耐用年数の償却率×経過月数÷12
それぞれの償却率は、以下に紹介する「減価償却資産の償却率等表」を参照してください。
国税庁:減価償却資産の償却率等表
関連リンク:アパートの減価償却とは?計算方法や節税方法を解説
軽量鉄骨造アパートの経営のポイント
ここでは、軽量鉄骨造アパートを経営する際のポイントについてお伝えします。
軽量鉄骨造アパートの建築コストは、費用対効果を考えて
軽量鉄骨造アパートの経営を考える際には、費用対効果を考慮した上で建物の仕様を決めることが大切です。
軽量鉄骨造は建築コストが安い分高級感に欠けるため、家賃が低く設定されやすい傾向があります。
一方、建築コストをかけて建物の性能を高めれば、その分家賃の設定を上げることが可能ですが、ターゲットとする層のニーズに合わなければコスト倒れになるリスクもあります。
アパートを建築する際には、自身の目的や地域のニーズに合った構造は何か専門家に相談するとよいでしょう。
費用計上を適切に行う
軽量鉄骨造アパートの経営を成功させるには、毎年の費用計上を適切に行うことで、発生する税金を抑えることも重要なポイントになります。
アパートの経営によって得た所得は、毎年税務署に申告して所得税などの税金を納めなくてはなりません。
その際の所得は収益から費用を差し引いて計算するので、計上できる費用が多いほど所得が抑えられ、税金も少なくなります。
- アパートの減価償却
- アパートローンなどにかかる利息(アパートローンの元本部分は経費として計上できません。)
- アパート経営に必要な管理費
- アパートの修繕費
など、計上できる費用は適切に処理することで、税金を抑えることが可能です。
キャッシュフローの管理を怠らない
アパートの経営においては、キャッシュフローの管理を怠らないということも大切なポイントです。
例えば減価償却費は、建物を取得した時点の取得原価を効果が及ぶと考えられる期間に配分する手続きです。建物を取得した時点でキャッシュアウトが生じていますが、毎年の費用計上の時点ではキャッシュアウトは生じていません。
また、アパートローンなどを利用して建物を取得した場合には、毎年の返済額はキャッシュアウトがあっても費用として計上することは認められていません。
このように、会計上の利益と手元に残るキャッシュフローの金額とは、必ずしも一致しないことに注意が必要です。
アパート経営には、定期的な修繕や原状回復費用、ニーズの変化に合わせたリフォームのための費用などが必要な場面も生じます。
必要なときに資金が足りないというような事態にならないように、キャッシュフローの管理を怠らないようにしましょう。
メンテナンスコストなども把握して、長期的な経営計画を立てる
軽量鉄骨造は鉄筋コンクリート造や重量鉄骨造に比べると耐久性がそこまで高くないため、大規模修繕などのメンテナンスが不可欠となります。
大規模修繕の費用は、建物の資産価値を維持するために不可欠の費用であり、一度に大きなキャッシュアウトが生じるので、計画的に備えておく必要があります。
このようなさまざまなコストをしっかり把握して、長期的な経営計画を立てることが、軽量鉄骨造アパートの経営のポイントとして非常に重要といえるでしょう。
新たにアパートを建てる際には、複数の建築会社を比較する
アパートの経営を成功させるには、できる限りコストを抑えて性能の優れた建物を建築してくれる建築会社を見つけることも大切です。
建築会社によって得意な分野は異なりますし、多くの物件を手掛けている会社ほど資材の仕入れコストが低くなるので、複数の建築会社に見積もりをとって比較することをおすすめします。
軽量鉄骨造の注意点にも留意する
軽量鉄骨造は鉄筋コンクリート造に比べると柱の強度が弱いため、建物を面で支える構造になっています。
そのため新築時にも間取りの柔軟性がなく、将来リフォームする際には大幅な間取りの変更ができないというデメリットに注意が必要です。
それに対して、柱と梁で建物を支えることが可能な鉄筋コンクリート造では間取りの自由度が大きく、遮音性の面でも優れているため、グレードの高い建物を建てることができます。
また、軽量鉄骨造の法定耐用年数は27年、鉄筋コンクリート造の法定耐用年数は47年とされています。
法定耐用年数は物理的な耐用年数と一致するものではありませんが、一定の目安とすることはできます。
軽量鉄骨造の初期費用は鉄筋コンクリート造よりも安くなるとしても、長期に渡る賃貸経営を考えた時、トータルでのコストパフォーマンスを考慮し、軽量鉄骨造と鉄筋コンクリート造のどちらを選択するか、再考することも大切です。
土地活用一筋54年。累計着工戸数120,000戸超の実績。
冊子をプレゼント
軽量鉄骨造で法定耐用年数を超えた経営をするには
最後に、軽量鉄骨造で法定耐用年数を超えた賃貸経営をするために大切な考え方を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
定期的なメンテナンスや修繕などを怠らないこと
法定耐用年数を超えても失敗なく賃貸経営を継続していくには、定期的なメンテナンスや修繕などを怠らないことが重要です。
法定耐用年数は、あくまで税金を算定するために減価償却費を計上するための基準となる年数であり、建物の物理的な耐用年数とは異なるものです。
建物の現実の耐用年数は、個々の建物の構造や建材、設備などの違いのほか、建物の使用方法や周辺の環境などの違いによって差が開きます。
そのため、定期的に適切なメンテナンスや修繕を行うことで物理的な耐用年数を延ばすことにつながり、法定耐用年数を超えた賃貸経営を実現することができるでしょう。
長期的な視野で資金管理を行うこと
法定耐用年数を超えると、減価償却費を経費として計上できなくなるので、税金の負担が増えることになります。
さらに、築年数が経過することで建物や設備の経年劣化が進み、修繕などのメンテナンスコストは大幅に増えていきます。
減価償却費の計上にはキャッシュアウトが伴わなかったのに対して、修繕費などの支出は現実にキャッシュアウトを伴いますので、手元のキャッシュフローは減少していきます。
建物や設備の老朽化や陳腐化などにより、賃料が減少していくことも織り込む必要があります。
軽量鉄骨造で法定耐用年数を超えた経営を行うには、このような事態を想定して長期的な視野で経営計画を立て、資金管理を行うことが重要なポイントといえます。
ただし、すでに減価償却も終わっている場合や収益力が低下している場合には、建て替えも視野に入れる必要があるでしょう。
土地活用のご相談は生和コーポレーションへ
アパート経営では、適切な資金計画や市場調査などが必要不可欠と言えますので、最適な土地活用はプロに相談するのがおすすめです。
生和コーポレーションは、土地活用一筋で半世紀にわたる実績とノウハウを蓄積してきました。
土地活用のご相談は、生和コーポレーションへご相談ください。
有効な土地活用をご提案させていただきます。
まとめ
この記事では、軽量鉄骨造の耐用年数や減価償却の考え方、アパート経営のポイントなどについて解説してきました。
耐用年数の考え方には、
- 法定耐用年数
- 物理的耐用年数
- 経済的耐用年数
という3つの考え方があることを解説しました。
法定耐用年数は、減価償却手続きを行う際に税法上使われる耐用年数です。実際の耐用年数とは異なることが一般的ですが、アパート経営を考える際の重要なポイントの一つになるといえるでしょう。
軽量鉄骨造は、建築コストの安さや工期の短さなどから、戸建て住宅やアパートなどでよく見られる工法です。
一方で軽量鉄骨造は耐久性が低く、メンテナンスが必要不可欠であることには注意が必要です。そのため軽量鉄骨造でアパート経営するときには、長期的な事業計画を立てることが重要となります。
アパート経営を考えている方はぜひ当社にご相談ください。
よくあるご質問
- アパート・マンション経営にはどのようなリスクがあるのですか?
- 主に空室リスクや老朽化による修繕、家賃の滞納などがあります。生和コーポレーションは入居者募集から長期修繕計画の立案、入居者様の対応など、オーナー様のアパート・マンション経営をトータルでサポートしています。
- 土地活用・不動産経営は初心者なのですが、どのように相談をおこなえばよいでしょうか?
- 弊社HPの電話もしくはお問い合わせフォーム・資料請求フォームから、お気軽にお問い合わせください。ご要望に応じて、オンライン面談・電話・メール等での対応が可能です。
- 生和コーポレーションの土地活用・不動産経営には、どのような特徴があるのですか?
- 4大都市圏での営業に特化し、土地活用一筋50年を超えております。マンション・アパートの累計着工戸数は100,000戸を超え、都市部に強い生和だからこそ、サブリース・一括借上げの入居率98%台を実現しています。
- お問い合わせ後の流れはどのようになっているのですか?
- お問い合わせ頂いた電話番号もしくはメールアドレスに担当がご連絡致します。
お客様のご相談内容に応じて、経験・知識が豊富な担当が対応致します。