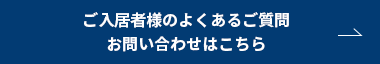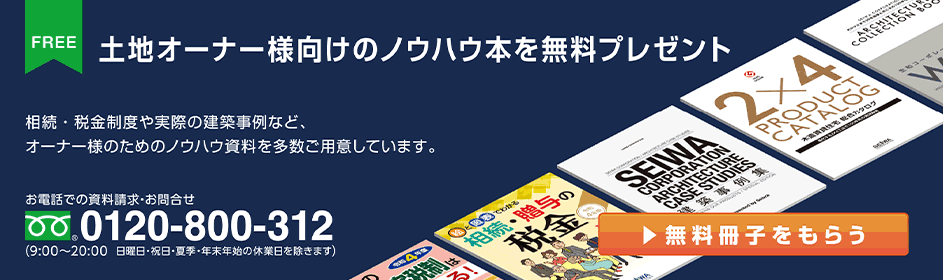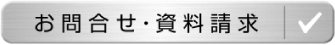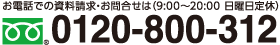木造アパートと聞くと、「音が響きやすい」「地震や火災に弱い」といったイメージが浮かぶ方もいるのではないでしょうか。しかし、近年の建築基準法改正や技術革新により、遮音性・耐震性・耐火性は大きく向上し、安心して住める住環境が整っています。
また、木造アパートは建築費やメンテナンス費を抑えやすいというメリットもあり、賃貸経営を始めるうえで魅力的な選択肢の一つです。
一方で、木造ならではの注意点もあります。したがって、これから木造アパートを建てて賃貸経営を始めたいと考えているのなら、メリットだけでなく、デメリットを解消するための対処法を把握しておくことも大切です。
この記事では、木造アパートのメリットや注意点、具体的な対策について詳しく解説します。
この記事の目次
木造アパートの性能の変化
近年の木造アパートは、性能やデザインの面で大きく進化しています。その背景にあるのは、建築基準法の改正です。1981年の改正では新耐震基準が導入され、震度6強~7程度の地震でも倒壊しない設計基準が設定されました。
そして2000年の改正により、接合部への金具の取り付けや耐力壁の配置バランスなど木造住宅に対する耐震基準がさらに強化され、耐震性が大幅に向上しました。
木造建築のおもな工法には、「軸組工法(在来工法)」と「2×4(ツーバイフォー)工法」があり、木造アパートでも広く採用されています。最近ではCLT(直交集成板)などを活用した高層木造建築物も登場していますが、コストや施工の面でまだ一般的ではなく、現在の木造アパートでは軸組工法と2×4工法が主流です。
本記事では、軸組工法と2×4工法を用いた3階建てまでの木造アパートに焦点を当てて解説します。
また、最新の木造アパートは、高い耐火性やスタイリッシュな外観を備えた高機能物件も増えています。
一口に木造アパートといっても築年数や工法によって性能は異なるため、入居者ニーズやコストバランスを考慮し、適切な仕様を選ぶことが重要です。
木造アパートのメリットとは?
木造アパートのメリットは、以下の5つです。
- 建築費やメンテナンス費を抑えやすい
- 狭小地や形状が不規則な土地などにも建てられる
- 天然の調湿効果がある
- 火災に強く倒壊しにくい
- 減価償却の期間が短い
それぞれについて詳しく解説します。
建築費やメンテナンス費を抑えやすい
木造アパートは、鉄骨造(S造)や鉄筋コンクリート造(RC造)に比べて建築費用を抑えられることが特徴です。
国税庁のデータによると、建物の構造別の坪単価(全国平均)は次のようになっています(1坪=約3.3平方メートルで換算)。
- 木造:坪単価約68万円(1平方メートル当たり20万7,000円)
- 鉄骨造:坪単価約97万円(1平方メートル当たり29万4,000円)
- 鉄筋コンクリート造:坪単価約100万円(1平方メートル当たり30万4,000円)
出典:国税庁「地域別・構造別の工事費用表(1㎡当たり)【令和6年分用】」
木造は軽量なため、地盤改良費や基礎工事費を削減できる点もコストダウンに貢献します。工期も短く、人件費を抑えることにもつながるのがメリットです。
また、木造アパートは修繕がしやすくメンテナンス費用も比較的安く済むため、老朽化への対応コストを最小限に抑えられます。
生和コーポレーションでは、ムダを省きつつデザインや機能性にこだわり、コストを抑えた高品質な建築を実現しています。
狭小地や形状が不規則な土地などにも建てられる
木造アパートは、多様な土地条件や入居者ニーズに対応できます。木材は加工性に優れているため、鉄筋コンクリート造を建てにくい狭小地や不整形地、低層住居専用地域でも対応でき、土地選びの幅を広げられるのがメリットです。
ただし、キャッシュフローの面では、ある程度の広さがあり、かつ整形地であるほうが土地活用の選択肢が広がって有利となるため、建設計画時には立地や敷地条件を考慮することが重要です。
生和コーポレーションでは、地域特性やターゲット層に応じた最適な間取りプランを豊富にご用意しています。家具が配置しやすい動線計画や、専有面積を無駄なく活かす設計により、快適で魅力的な住空間を実現します。
天然の調湿効果がある
木造アパートは、木材の自然な調湿効果により快適な住環境を実現できます。湿度の高い夏には余分な湿気を吸収し、乾燥する冬には適度な湿気を放出することで、室内の湿度を安定させる役割を果たします。
木材の特性が日本の気候風土に適しており、季節を問わず快適な室内環境を保ちやすいため、居住者にとって魅力的な住空間を提供できる点もメリットです。
火災に強く倒壊しにくい
木造アパートは火災に弱いという印象を持たれがちですが、実際には火災に強い特性を持っている点も特徴の一つです。
木材は燃えると表面が炭化し、この炭化層が内部を保護して燃え広がる速度を遅らせるため、急激な建物の崩壊を防ぎます。一方、鉄骨は高温になると急激に強度を失い、建物が崩壊するリスクが高まります。
また、石膏ボードなどの不燃材料の採用により、火災の広がりを抑えられる点も木造アパートの利点です。適切な耐火処理が施された木材や建材を使えば、さらに安全性を高めることが可能です。
減価償却の期間が短い
木造アパートは法定耐用年数が22年と比較的短く、減価償却を早期に進められる点で税制面のメリットがあります。
減価償却とは、建物の購入費用を耐用年数で分割し、経費にする仕組みです。経費として計上できる金額が大きくなれば、その分、所得税の納付額を抑えられます。
例えば、9,000万円の木造アパートの場合、年間約409万円を経費に計上することが可能です。一方、建築費用を同じ9,000万円と仮定すると、重量鉄骨造(耐用年数34年)では約265万円、鉄筋コンクリート造(耐用年数47年)では約191万円となり、計上額に差が生じます。
減価償却期間が短い木造アパートは、賃貸経営初期のキャッシュフローを重視する方や、早期に税制面のメリットを得たい方に適しています。
木造アパートの注意点と対処法

木造アパートの注意点には、木材が湿気を吸収しやすいこと、シロアリや菌による被害を受けやすいこと、気密性が比較的低いことが挙げられます。
それぞれの注意点と対処法について解説します。
木材が湿気を吸収しやすい
先述のとおり、木材には湿気を適度に吸収する特性があります。ただし、雨が多かったり、湿度が高かったりする環境下では、木材が劣化や腐食するリスクもあるため、適切な施工や対策が必要です。
この問題を防ぐには、防腐薬剤の注入や基礎の高さの調整、壁の内部に通気層を設けるなどの対策が重要です。また、定期的な点検によって早期に問題を発見し、適切に対処することも、木造アパートを長持ちさせるコツといえます。
シロアリや菌による被害を受けやすい
木材がシロアリや腐朽菌の餌となりやすい性質を持っていることも、木造アパートのデメリットの一つです。
基礎部分や床下から侵入するシロアリが構造材を食害すると、建物の強度が低下するリスクがあります。対策としては、建築時に防蟻処理を施すことが挙げられます。防蟻処理の効果を維持するためには、5年程度の周期で再処理を行なうことが必要です。
気密性が比較的低い
木造建築は鉄筋コンクリート造に比べて気密性が低く、外気の影響を受けやすい特性があります。ただし、2×4工法のように構造自体が気密性を高めやすい工法もあり、すべての木造アパートが気密性に劣るわけではありません。
気密性を高めるには、高性能な断熱材の使用や二重窓(二重サッシ)が効果的です。
例えば、生和コーポレーションの木造アパートでは、窓ガラスの片側に特殊金属膜をコーティングした「Low-E 複層ガラス」を採用しています。このガラスは、夏は陽ざしの熱をシャットアウトするとともに紫外線をカットし、冬は室内の暖かさを逃しにくくする効果があります。この仕様は「次世代省エネ等級4」をクリアしており、断熱性を高め、冷暖房効率を向上させます。
このように、適切な対策を講じることで、快適な室内環境を実現することが可能です。
土地活用のご相談、まずはお気軽に。相談から物件管理まで一貫したサポートを提供。
木造アパートによくあるQ&A

木造アパートについて、「地震に弱いのでは?」「音が響きやすいのでは?」と不安を感じる方もいるかもしれません。ここでは、2つの疑問について解説します。
木造アパートは地震に弱い?
木造アパートは地震に弱いと思われることがありますが、現行の耐震基準に適合した建物は十分な耐震性を備えています。
特に、2000年の建築基準法改正により、木造建築物の耐震性能は大きく向上しました。
また、2×4工法のようなモノコック構造を採用した建物は、壁や床が一体となっており、面全体で地震の力を分散・吸収する仕組みを持っています。そのため、揺れへの耐性が強く、地震による倒壊リスクを低減できます。
木造アパートは音が響きやすい?
木造アパートは音が響きやすいイメージがあるかもしれませんが、防音素材の使用や構造の選択によって大きく改善できます。
特に、2×4工法は外壁が多重構造となっているために遮音性が高く、外部や隣室からの音を遮る効果があります。また、遮音材の使用や二重窓の採用、カーペットや防音マットの設置などの対策を講じると、より防音性を高めることが可能です。
適切な防音対策を施すことで、木造アパートでも生活音や騒音問題のリスクを軽減できます。
生和コーポレーションの木造アパートの特徴
生和コーポレーションの木造アパートは、耐震性・耐火性・断熱性・遮音性に優れた2×4工法を採用しています。
この工法は、壁や床などの面で建物を支えるモノコック構造の一種です。地震の揺れに強く、阪神・淡路大震災でも倒壊率ゼロを記録しています。
また、900度以上の熱に1時間以上耐えられる防火サイディングを使用し、高い耐火性を実現しています。さらに、優れた断熱技術や遮音技術を備え、快適な住環境を提供します。
デザイン面でも優れており、例えば外付けエントランスを採用することで、木造アパートの魅力を高めています。木造集合住宅では、エントランスを設けないか、単なる入口として機能する程度の仕様が多いのが一般的です。しかし、生和コーポレーションの木造アパートではエントランスを設けることで、品格ある佇まいを備えた心地良い空間を実現しています。
まとめ:土地活用なら生和コーポレーションにご相談ください
最新の耐震基準に基づいて建てられた木造アパートは、優れた耐震性を備えています。また、2×4工法の木造アパートには耐火性や遮音性などに優れているメリットもあります。
一方で、木材が湿気を吸収しやすい、シロアリ被害を受けやすいなどの点には注意が必要です。そのため、賃貸経営を成功させるには、木造アパートならではのデメリットを解消できる、確かな実績と専門的なノウハウを持つ建築会社を選ぶことが大切です。
50年以上にわたって土地活用事業を展開している生和コーポレーションでは、賃貸経営のトータルサポートを提供しています。
設計・施工はもちろん、入居者募集や管理運営まで、一貫した支援体制でオーナー様の賃貸経営をサポートしているため、土地活用で木造アパート経営をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
関連リンク:生和のアパート経営事例はこちら
よくあるご質問
- アパート・マンション経営にはどのようなリスクがあるのですか?
- 主に空室リスクや老朽化による修繕、家賃の滞納などがあります。生和コーポレーションは入居者募集から長期修繕計画の立案、入居者様の対応など、オーナー様のアパート・マンション経営をトータルでサポートしています。
- 土地活用・不動産経営は初心者なのですが、どのように相談をおこなえばよいでしょうか?
- 弊社HPの電話もしくはお問い合わせフォーム・資料請求フォームから、お気軽にお問い合わせください。ご要望に応じて、オンライン面談・電話・メール等での対応が可能です。
- 生和コーポレーションの土地活用・不動産経営には、どのような特徴があるのですか?
- 4大都市圏での営業に特化し、土地活用一筋50年を超えております。マンション・アパートの累計着工戸数は100,000戸を超え、都市部に強い生和だからこそ、サブリース・一括借上げの入居率98%台を実現しています。
- お問い合わせ後の流れはどのようになっているのですか?
- お問い合わせ頂いた電話番号もしくはメールアドレスに担当がご連絡致します。
お客様のご相談内容に応じて、経験・知識が豊富な担当が対応致します。
他の「アパート経営で悩んだときは」の記事を見る
-
 土地活用法を考える際、アパート経営を検討したことがある土地オーナーも少なくないでしょう。 節税効果の高さや安定した家賃収入は、アパート経営の大きなメリットです。ただ、アパート経営にかかる費用や、建設後…
土地活用法を考える際、アパート経営を検討したことがある土地オーナーも少なくないでしょう。 節税効果の高さや安定した家賃収入は、アパート経営の大きなメリットです。ただ、アパート経営にかかる費用や、建設後… -
 名古屋での賃貸経営を検討している方のなかには、名古屋がマンション経営・アパート経営に適する理由や、賃貸経営に向いているエリアを知りたいと考える方もいるでしょう。 名古屋は人口の増加や経済規模の拡大が期…
名古屋での賃貸経営を検討している方のなかには、名古屋がマンション経営・アパート経営に適する理由や、賃貸経営に向いているエリアを知りたいと考える方もいるでしょう。 名古屋は人口の増加や経済規模の拡大が期… -
 福岡に土地を所有している方のなかには、「マンションやアパートの経営に興味がある」という方も少なくないでしょう。 ただ、本当に儲かるのか、経営するならどのエリアを選ぶべきかなどで悩んでいる方もいるかもし…
福岡に土地を所有している方のなかには、「マンションやアパートの経営に興味がある」という方も少なくないでしょう。 ただ、本当に儲かるのか、経営するならどのエリアを選ぶべきかなどで悩んでいる方もいるかもし… -
 東京都はマンション・アパート経営に向いているといわれますが、その理由はどこにあるのでしょうか。 マンション・アパート経営における東京都の強みは、人口流動性の高さです。人口が多く、かつ人口の流出入が激し…
東京都はマンション・アパート経営に向いているといわれますが、その理由はどこにあるのでしょうか。 マンション・アパート経営における東京都の強みは、人口流動性の高さです。人口が多く、かつ人口の流出入が激し… -
 マンション経営・アパート経営では立地が重要といわれていますが、大阪府はマンション経営・アパート経営に向いているのでしょうか。 大阪府のほぼ中央に位置する大阪市は人口が転入超過傾向にあるほか、国内外への…
マンション経営・アパート経営では立地が重要といわれていますが、大阪府はマンション経営・アパート経営に向いているのでしょうか。 大阪府のほぼ中央に位置する大阪市は人口が転入超過傾向にあるほか、国内外への…