アパート建築費用の相場はいくら?内訳や計算方法、安く抑えるポイントなどを解説!
賃貸アパートを建築する際に必要となる情報の一つとして、建築費用が挙げられます。賃貸アパートの建築費用については、建物の構造や規模、地域によっても違いがあるため、建物の構造や地域ごとの相場費用を確認することが大切です。
賃貸アパートの建築費用を具体的に算出したいと思っても、アパート建築全体にかかる費用の内訳などはわかりづらいものです。そのため、賃貸アパートの建築費用の情報を収集する際に、何から手をつけたらいいのかわからず困っている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、賃貸アパート建築費用の概要や相場、建築費の計算方法や注意点などをまとめています。賃貸アパートを経営する際や、賃貸アパート建築の検討段階での資料として、ぜひお役立てください。
この記事の目次
賃貸アパートの建築費用に含まれるものは建築会社によって異なる
最初に、賃貸アパートの建築費用について解説します。
賃貸アパートの建築費用とは、文字通り、賃貸アパートとして使用する建物を建築するために必要な費用のことです。外観や内装の設計費をはじめ、建物を建築し、入居者が必要となるトイレや浴室、台所などの住宅設備を整えるまでの工事に該当する費用などが対象になります。
ただし、建築費用に含まれるものの定義は曖昧で、どこまでの工事が建築費用に該当するかの考え方は建築会社によって異なります。建築会社に見積もりを依頼するなどして比較・検討を行う際には、建築工事に含まれるものの内訳までよく確認するようにしましょう。
《項目別》アパートの建築費用の相場はいくら?
アパートの建築費用相場は、以下の3つの要因によって変わります。
- 構造
- 立地
- 坪数
ここでは、それぞれの要因を踏まえてアパートの建築費用相場を解説します。
構造
アパートの構造は、主に木造・軽量鉄骨造・鉄筋コンクリート造の3つに分類されます。それぞれの坪単価や特徴、メリット、デメリットは下表の通りです。
| 木造 | |
| 坪単価 | 75万~95万円程度 |
| 特徴 | アパートの建築構造の中で比較的多い建築構造 |
| メリット |
|
| デメリット |
|
| 軽量鉄骨造 | |
| 坪単価 | 90万~120万円程度 |
| 特徴 | 厚さ6ミリメートル未満の鋼材を用いた構造で、主にプレハブ工法が採用される |
| メリット |
|
| デメリット | 耐火性や遮音性、断熱性が劣る |
| 鉄筋コンクリート造 | |
| 坪単価 | 105万~145万円程度 |
| 特徴 | 鉄筋とコンクリートを組み合わせた構造で「RC造」とも呼ばれる |
| メリット |
|
| デメリット |
|
すべての構造に共通しますが、土地や建物の形状、地盤の状況などによって、上記の建築費用の相場が大きく変わるケースがあります。その点も踏まえて、アパートを建築する際には建築会社とよく相談しながら進めると良いでしょう。
立地
地盤が緩い土地にアパートを建てる場合は、固い支持地盤までセメント系凝固材を注入したり、鋼管杭を埋め込んだりするなどの地盤改良工事が必要です。状態が悪い地盤ほどより強固な地盤改良工事が必要となるため、必然的にアパート建築にかかる総費用も上がってしまいます。
また、道路が狭い場所や交通量が多い場所では、工事車両の出入りが不便です。そのため、人力で材料を搬入する手間がかかったり、道路を交通規制するための現場管理費が余計に発生したりすることで、建築費が上がる傾向にあります。
坪数
アパートの建築費は、建築を予定する建物の延べ床面積によっても変動します。
延べ床面積とは、建物におけるすべての階数の床面積を足した面積です。例えば、2階建てアパートの各階の床面積が50坪であれば、延べ床面積は「50坪×2階=100坪」となります。
こうして求めた延べ床面積に坪単価をかければ、おおよその建築費を算出できます。
なお、建築における面積には「延べ床面積」「施工面積」「容積対象面積」など複数の種類があります。施工面積とは、バルコニーや玄関ポーチ、吹抜けなどを含む面積です。延べ床面積にはこれらの面積は含まれないため、施工面積のほうが広くなります。
容積対象面積とは、建物の容積率を計算する際に用いる床面積で、マンション賃貸部や共用部なども加算されます。
アパートの建築費を算出する際は、どの面積を基準にしているかを確認することが大切です。
アパート建築費用の主な内訳
アパート建築費用は、主に以下の項目で構成されます。
- 設計費
- 本体工事費
- 付帯工事費
- 諸費用
ここでは、アパート建築費用について4つの項目別に解説します。
設計費
設計費とは、建物の設計を建築会社などへ依頼した際にかかる費用を指します。アパートの規模や建物の複雑性、設計事務所の設定などによって相場は変動しますが、一般的にはアパート建築費全体の約3%です。ただし、設計費に確認申請料が含まれていなかった場合には、別途費用がかかる可能性があります。
また、本体工事費に設計費を含むケースもあるため、事前に確認して明確にすることが大切です。
本体工事費
本体工事費は、アパートの建築そのものにかかる費用で、「本体価格」と呼ばれることもあります。本体工事費の内訳には、アパートの躯体工事だけでなく内装や外装工事、トイレ・浴室などの設備設置にかかる費用も含まれ、アパート建築費用全体の80~90%を占めるケースが一般的です。
ただし、本体工事費に含まれる項目は建築会社によって異なるため、見積もりの段階で細かく確認しておくことが重要です。
付帯工事費
付帯工事費とは、外構工事や地盤改良工事、土地の造成工事など、アパート本体の建築とは別にかかる費用です。一般的な相場はアパート建築費用の5~10%程度ですが、土地の広さや状態、ライフラインの整備状況などによって変動します。
例えば、前述したように、地盤が緩い土地では別途地盤改良工事費用を負担する必要があります。また、前面道路に埋設されている上・下水道管やガス管を敷地内に引き込む距離が長くなると、材料費や工事費が余計にかかって費用が高くなります。
諸費用
アパートを建築する際には、建築自体にかかる費用以外に、アパートローン手数料や司法書士への報酬、各種税金(不動産取得税・印紙税・登録免許税など)もかかります。これらの費用がアパート建築費用に占める割合は、全体の5%程度です。
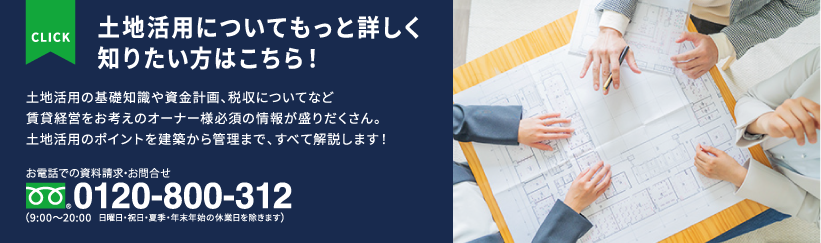
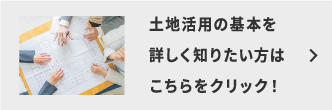
アパート建築に必要な自己資金の目安
アパートを建築するにあたり、建築代金の全額を金融機関からの融資によってまかなう事例は少なくありません。そのため、自己資金がなくてもアパートを建築できるケースもあります。
ただし、アパートの建築に際してかかる諸費用は基本的に自己資金で支払わなければならないため、その分の自己資金は事前に用意しておく必要があります。
用意しておきたい自己資金の相場は、建築費全体の5%程度です。例えば、建築費1億円のアパートを建てる場合は、500万円を目安として自己資金を用意することになります。
なお、アパートローンを組むには、金融機関による審査に通過しなければなりません。自己資金が多ければ借入金額が少なくなり、年収に対する返済負担率が低くなるので、より金融機関の審査に通過しやすくなります。ただし、建築段階で自己資金を投入しすぎると、修繕費用を捻出できないなどアパート経営時の維持管理に影響が出る恐れがあるため、将来の資金繰りも踏まえて十分に検討することが肝要です。
アパート建築の工期の目安
アパート建築にかかる工期は、構造によって異なります。例えば、木造や軽量鉄骨造の場合は「階数+2~4ヶ月」、鉄筋コンクリート造(RC造)は「階数+3~6ヶ月」が目安です。
ただし、外構工事や地盤改良工事などの付帯工事が追加されると、施工完了までの工期が延びます。場合によっては、建築中に見つかった地中埋設物を除去するなどの工事が別途発生することもあるでしょう。そのため、アパートを建築する際は、ゆとりを持ったスケジュールを設定することが大切です。
《構造別》アパート建築費用シミュレーション
前述のように、アパートのおおよその建築費用は「坪単価×延べ床面積」の計算方法で算出できます。坪単価は、面積当たりの設備数によって変動するため、間取りが多くなるほど高くなるケースが一般的です。
例えば、同じ建物に1Kを多く入れた場合、2LDKを多く入れるよりも戸数が増えるため、設備費も多くなります。つまり、2LDKより1LDKのほうが坪単価は高くなり、1Kになるとさらに単価が上がるイメージです。
なお、ファミリー向け賃貸アパートに適した3LDKの広さは、70~75平方メートル(約20~22坪)ほどが一般的です。
ただし、延べ床面積は各階の床面積の合計となるため、正確な数値は建築するにあたって建築会社から提案を受けるまでは、はっきりとわかりません。概算値であれば、建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)から推測することができます。
また、構造によって坪単価は異なるので、同じ坪数であっても木造なのか、軽量鉄骨造なのか、鉄筋コンクリート造なのかによって建築費用が変動する点も押さえておきましょう。
ここでは、延べ床面積が200坪のアパートを建築した場合の費用を、構造別にシミュレーションします。
木造2階建てアパート
| 坪単価 | 80万円 |
| 延べ床面積 | 200坪 |
| 戸数 | 5戸×2階 |
| 建築費用 | 80万円×200坪=1億6,000万円 |
木造は、その他の構造よりも建築費用を抑えられる構造です。そのため、アパート経営を始めるにあたって初期費用を抑えたい方に向いています。
軽量鉄骨造3階建てアパート
| 坪単価 | 100万円 |
| 延べ床面積 | 200坪 |
| 戸数 | 3戸×3階 |
| 建築費用 | 100万円×200坪=2億円 |
軽量鉄骨造のアパートは規格化された材料を現場で組み立てて建築することが多く、鉄筋コンクリート造と比較すると建築費用を抑えられる構造です。単身者だけでなく、ファミリー向けに広めの部屋を確保すると、家賃を高めに設定できてより収入を上げやすくなります。
鉄筋コンクリート造3階建てアパート
| 坪単価 | 120万円 |
| 延べ床面積 | 200坪 |
| 戸数 | 3戸×3階 |
| 建築費用 | 120万円×200坪=2億4,000万円 |
鉄筋コンクリート構造(RC構造)は、他の構造よりも坪単価が高い傾向にあります。建築費用も高くなりますが、他の構造よりも耐震性や耐久性などの住宅性能が優れているため、家賃を高めに設定しやすい点が特徴です。
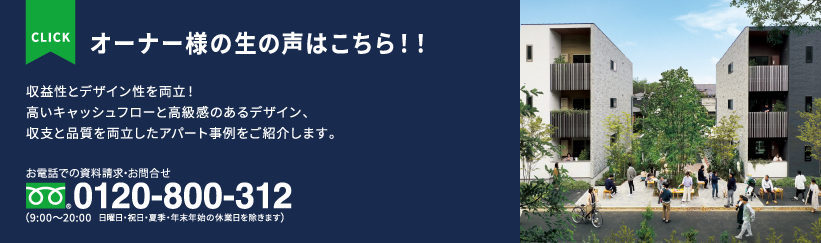
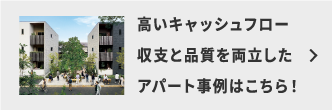
賃貸アパート建築のための融資活用方法
賃貸アパートを建築する際は、アパートローンを活用するケースが一般的です。アパートローンは都市銀行や地方銀行、信用金庫、信用組合などが提供しており、それぞれに特徴が異なります。各金融機関の特徴は以下の通りです。
| 金融機関 | 特徴 |
| 都市銀行 | 融資の基準が厳しい反面、金利が低め |
| 地方銀行 | 都市銀行と比べて融資基準が低め |
| 信用金庫・信用組合 | 地域に根ざした金融機関であり融資のハードルは低いが、金利は高め |
なお、アパートローンには、万が一返済ができなくなった場合に代位弁済してくれる保証会社が入ることがあります。一方で、保証会社を介さず、金融機関が自社でリスクを負担する手段が「プロパーローン」です。プロパーローンは一部の地方銀行や信用金庫、信用組合などで提供されているもので、保証会社の審査基準ではなく、金融機関が独自に設定した基準をクリアできれば融資が認められます。
一般的な保証会社の保証付きローンの審査が通らなかった場合は、プロパーローンを検討するのも良いでしょう。
アパートローンと住宅ローンの違いとは
アパートローンとは、居住以外の目的の投資用としてアパートやマンションなどの物件を購入・建築する際に利用できる融資商品です。銀行や信託銀行、信用金庫、JAバンク、ノンバンクなど、多数の金融機関が取り扱っており、集合住宅の建築、購入のどちらにもアパートローンを利用できます。原則的に、満20歳以上の個人が借り入れの対象となっていますが、法人が利用できる場合もあります。
それに対して、住宅ローンとは自らが居住するための住宅を購入する時に使える融資であり、アパートを建築する際には利用できません。
アパートローンの利用を検討する際には、家賃収入での利益面と、管理費・積立修繕費・税金などの支出面をきちんと把握し、計画を立てた上で申し込むようにしましょう。
アパートローンには大きく分けて、民間の金融機関が提供するものと、住宅金融支援機構などの公的機関が提供するものがあり、特に民間の金融機関にはプランが豊富に用意されています。
アパートローンの金利方式には、大きく分けて、変動金利型と固定金利型の2つの種類があります。変動金利型は、ローンの金利が半年ごとに見直され、返済額についても5年に一度見直しが行われる金利方式です。固定金利型は、ローン返済中の金利が事前に定められた金利方式です。
アパートローンを借りる時の注意点とは
賃貸アパートを建築する際には住宅ローンが利用できず、アパートローンを借りることになります。その際の注意点を押さえておきましょう。
複数の金融機関に相談をして、比較をする
アパートローンは、金融機関ごとに事業性の評価方法や基準が異なるため、融資額に大きな差が発生することがあります。ある金融機関から満額融資を断られたとしても、別の金融機関で満額融資が可能になるケースもめずらしくありません。そのため、必ず複数の金融機関に相談して、比較するようにしましょう。
収益に関するシミュレーションまでしてくれる建築会社に頼むのが良い
アパートローンを利用する際には、先々まで見通した収益計画と、無理のないローンの返済計画が重要になります。見通しの甘い収益計画を思い描くと、思ったような収益を得られず返済が滞ってしまう可能性もあります。しかし、専門家でない人がしっかりとした収益計画を立てるのは至難の業です。スムーズに融資を受けるためにも、収益計画に関するシミュレーションまで行ってくれる建築会社に依頼しましょう。
高騰している建築費用を安く抑える6つのポイント
近年、建築資材の値上げやエネルギーコストの増大、人材不足による人件費の高騰などに伴い、建築費が上昇しています。特に、人材不足は将来的にも解決の見込みがなく、今後も建築費が下がる可能性は低いでしょう。
また、日本の物価に大きな影響を与える円安も、建築費が高騰する要因の一つです。日本は建築資材のほとんどを輸入に頼っている状況にあり、このまま円安の影響を受けると建築費はさらに高騰してしまいかねません。
このような状況が続く中でアパートの建築費用を抑えるには、以下のポイントを把握しておくことが大切です。
- 建築するアパートの構造・条件を得意とする建築会社を選ぶ
- 建物をシンプルな形状にすることで費用を抑えられる
- 建築の際に譲れないポイントを明確にしておく
- 部屋の設備のグレードを見直す
- 諸費用のコストカットを検討する
- 補助金制度を活用する
ここでは、アパート建築費用を安く抑えるための各ポイントを解説します。
建築するアパートの構造・条件を得意とする建築会社を選ぶ
間取りが同じであっても、一般的に建築会社によって提示される建築費が変わってきます。構造や条件により、建築会社が得意な工事が異なります。
より良い物件を建築するために、まずは複数の建築会社へ見積もりを依頼し、比較・検討をしましょう。その際、建築会社の得意分野も細かく確認してください。アパート経営では、一度建築すると、20年~30年は管理しながら家賃収入を得ます。建築する建物は大切な資産になるので、なるべく信頼できる建築会社に依頼するようにしましょう。
建物をシンプルな形状にすることで費用を抑えられる
建物を建築する場合、建物が複雑な形になるほど、建築費用が多くかかります。反対に、真四角に近い形や汎用性の高い形のほうが、材料と手間が少なくなる傾向があり、費用を安く抑えられる可能性があります。
例えば、2階建ての賃貸アパートでは複雑な形より、1階と2階の床面積がほぼ等しい総2階のシンプルな形のほうが、部屋数を多く設けられます。それだけでなく、建築費用の観点からもコストパフォーマンスが良くなります。
建築の際に譲れないポイントを明確にしておく
アパート建築の見積もりを比較する際に重要なのは、譲れないポイントを明確にして検討することです。「物件の利回りは7%台を目指す」「予算を3億円以内に収める」など、なるべく具体的な条件を決めるようにしましょう。譲れないポイントを明確にすることで、必要な工事だけで済み、費用が抑えられる可能性が高くなるだけでなく、建築会社を選ぶ際の判断基準にもなります。
部屋の設備のグレードを見直す
アパートの入居者を集めるには、ある程度設備の充実を図る必要があります。しかし、キッチンやトイレ、オートロックなどの設備にこだわりすぎると、コストがかさむ点は否めません。
建築費用が想定よりも高くなった場合は、導入する設備の種類やグレードを見直すことが必要です。入居者の需要をイメージした上で、適切な設備を選びましょう。
諸費用のコストカットを検討する
アパートを建築する際には、建築そのものにかかる費用だけでなく、不動産取得税や印紙税、登録免許税といった税金、アパートローンにかかる手数料などの諸費用が発生します。諸費用の目安はアパート建築費用全体の5%程度ですが、できるだけ初期費用を抑えるためにはコストカットを考えることが大切です。
例えば、アパートローンにかかる手数料は金融機関ごとに異なります。少しでも諸費用を減らしたいのであれば、複数の金融機関の手数料を比較検討すると良いでしょう。
補助金制度を活用する
国や自治体が提供する補助金制度を活用する方法も、アパートの建築費用を抑えるポイントの一つです。
経済産業省では「ZEH(net Zero Energy House)」の普及を目指し、ZEH(ZEH+)に対応した住宅を新たに購入した方に対して補助金を支給しています。「ZEH」とは、太陽光発電を代表とする再生可能エネルギーによって、住宅で使用するエネルギーを実質ゼロになるように目指した住宅のことです。
ZEH関連の補助制度は多岐にわたり、戸建て住宅だけでなく集合住宅に関する補助金も多くあります。例えば、「低層ZEH-M促進事業」では、住宅用途部分が3階以下で条件を満たした集合住宅を建てると、1戸あたり40万円の補助を受けることが可能です。
省エネ住宅は、戸建て住宅ではポピュラーになりつつありますが、アパート経営ではそれほど多く見られません。そのため、省エネに関する取り組みは他のアパートとの差別化につながり、入居者を集めやすくなる可能性がある点もメリットです。
ただし、ZEH-Mの補助金を受けるには「ZEHデベロッパー」として登録された建築会社にアパートの建築を依頼しなければなりません。そのため、アパートを建築する際にZEH-Mの補助金を受けたいのであれば、建築会社がZEHデベロッパーに登録されているかどうかを確認することが大切です。
その他、子育て世帯が安心して暮らせる共同住宅の整備をサポートする「子育て支援型共同住宅推進事業」も活用しやすいでしょう。例えば、アパートのベランダに子どもの転落防止用の対策を講じると、1戸あたり最大で100万円の補助金を受け取れます。
建築依頼をする建築会社の選び方
アパート建築の依頼先は建設会社・ハウスメーカー・工務店などさまざまであり、それぞれの特性を踏まえた上で選ぶ必要があります。それぞれの特徴は以下の通りです。
| メリット | デメリット | |
| 建設会社 |
|
|
| ハウスメーカー |
|
|
| 工務店 |
|
|
また、建設会社を選ぶ際は、経営基盤が安定しているかどうかを確認することも大切です。事前に、公式サイトなどで設立年度や資本金などをチェックして、信頼できる会社を選定しましょう。併せて、自分が希望している建築構造の建築実績が豊富かどうかも、確認しておきたいポイントの一つです。
依頼後は、担当者との相性も重要なポイントとなります。例えば、こちらの要望にすべて対応してくれる担当者だから信頼できると感じていても、要望を伝えすぎたために無理が生じ、建築計画が破綻してしまう可能性も否めません。スムーズにアパート建設を進めるためにも、互いに会話のキャッチボールをしながら相談できる担当者を選びましょう。
賃貸アパート経営における収支シミュレーション
賃貸アパート経営は長期にわたる事業となるため、将来を見据えた計画を立てることが重要です。賃貸アパート経営における、収入や支出の予測、月々のアパートローン返済額の予測など、さまざまな条件でのシミュレーションを通して、賃貸アパート経営全体の収支予測を確認しておきましょう。
ここでは、賃貸アパート経営の収支シミュレーションに欠かせない、各種利回りの意味や計算方法をはじめ、収支シミュレーションの作成に便利なツールなどをご紹介します。
利回りの定義
利回りとは、初期費用に対して一定期間でどの程度のお金が返ってくるかを示すものです。一般的な利回りは、1年間の利回りである年間利回りを指します。
例えば、3億円をかけて建築したアパートが1年間で3,000万円の収入を生み出す場合は、3,000万円÷3億円で算出し、年間利回りは「10%」になります。
2つの利回りの計算方法
利回りには、表面利回り、実質利回りという2つの計算方法があります。それぞれの利回りの意味と、計算方法をご紹介します。
表面利回り
表面利回りとは、その物件の価格に対してどのぐらいの家賃収入が入ってくるかという表面的な収入を表すものです。維持管理費など、賃貸アパートの保有にかかるコストは計算外のため、実質的な利回りとは少々異なります。なお、満室を想定した収入を表す場合は想定利回りと呼ばれます。計算式は以下の通りです。
表面利回り=年間収入÷建築価格×100
表面利回りの計算で使用する年間収入や購入価格は、表面上のデータなので、簡易的に計算する際にも便利です。
実質利回り
実質利回りは、表面利回りに年間支出の要素をプラスした利回りのことです。購入や新築を検討する段階の場合、必ず実質利回りで計算するようにしてください。計算式は以下の通りです。
実質利回り=(年間収入-年間支出)÷建築価格×100
年間支出には、固定資産税や火災保険料、管理費や修繕費などが含まれます。このうち、修繕費などは物件の状態により発生する金額が異なるので、実質利回りを計算するためには知識や経験が必要です。
各利回りで登場した「建築価格」には印紙・仲介手数料・不動産取得税などを、「年間支出」には建物修繕費・火災保険料・固定資産税・都市計画税などを含む必要があります。なお、建築費用や年間支出の内訳は、きちんと建築会社に確認しておきましょう。
収支シミュレーションの作成
賃貸アパート経営のための収支シミュレーションを算出するといっても、電卓を使って一つひとつ計算していくのは大変です。その際に便利なのが、ネット上で使用できるシミュレーションツールの活用です。
以下にて、収支シミュレーションツールで算出した計算結果をご紹介します。 なお、計算を単純化するため、諸費用を除いた収支シミュレーションになっています。
| 【物件情報】 | 【資金計画】 |
| 建築費:3億円 | 自己資金:3,000万円 |
| 満室時想定年収:2,400万円 | 借入金額:2億7,000万円 |
| 想定空室率:10% | 借入期間:35年 |
| 諸経費率:15% | 借入金利:年利2% |
上記の条件の下、簡易収支シミュレーションを行った結果は以下の通りです。
| 返済額(月額) | 89万4,410円 |
| 返済額(年額) | 1,073万2,920円 |
| 返済総額 | 3億7,565万1,594円 |
| 家賃収入(年額) | 2,400万円 |
| 控除・諸経費(年額) | 600万円 |
| 年間支出 | 1,673万2,920円 |
| 年間手取り | 726万7,081円 |
| 表面利回り | 8.0% |
| 実質利回り | 6.0% |
| 返済後利回り(※1) | 2.5% |
| 投資利回り(※2) | 24.3% |
- ※1 家賃収入から諸経費、返済額を差し引いた、手取り家賃収入をもとに計算した利回り。計算式は、「返済後利回り=年間手取り÷建築価格」。
- ※2 投資した自己資金に対する利回り。計算式は「投資利回り=年間手取り÷自己資金」。
オンラインで利用できるシミュレーションツールは、使い勝手が良く、必要情報を入力するだけで収支シミュレーションを作成してくれます。ご自分で検索して試してみてはいかがでしょうか?
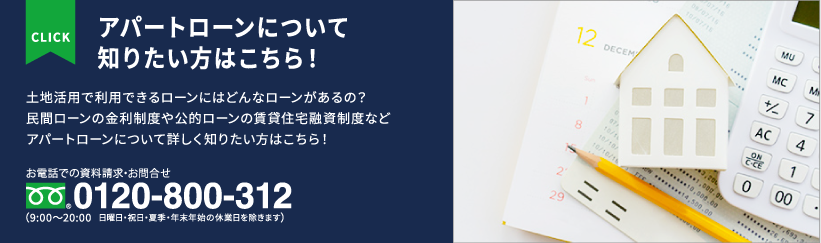
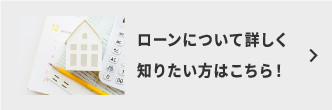
賃貸アパート経営なら生和コーポレーションにおまかせください!
賃貸アパートを建築するためには、専門家の力を借りることが重要です。
生和コーポレーションは、土地活用一筋、創業以来54年(2024年9月時点)にわたり、賃貸アパート経営をはじめとした土地の有効活用を通して、オーナー様とともに歩んでまいりました。賃貸経営に特化した建築会社として、マンション・アパートの累計着工戸数12万戸超の実績と、都市部に強い生和だからこそのサブリース・一括借上げの入居率98%台を実現しております。鉄筋コンクリート造、木造2×4ともに、建物の性能に高い評価をいただいています。
建築プランの作成や事業計画の作成まで無料で行っているだけでなく、建てた後のサポート体制も充実しています。アパート経営なら生和コーポレーションにまずはご相談ください。
アパート建築費用を把握し経営に有効活用しましょう
アパート建築費用の相場は、構造や立地、坪数によって異なります。例えば、木造は75万~95万円程度、軽量鉄骨造は90万~120万円程度、RC造は105万~145万円程度と、建物の耐久性に比例して建築費用相場も上がるケースが一般的です。
近年は、円安や人材不足などの影響を受けて、建築費用が高騰しています。できるだけコストを抑えるには、アパートを建築する前に予算や希望する構造、条件を踏まえて具体的な計画を立てた上で、信頼できる建築会社を選ぶことが大切です。
また、入居率や耐用年数を念頭に置いて、将来を見据えた構造を検討しましょう。
生和コーポレーションでは、土地活用や賃貸経営をサポートしています。アパート経営に関するお悩みは、ぜひ生和コーポレーションにご相談ください。
以下の記事では、アパート建築にかかわる建築基準法について解説しています。ぜひ、こちらもご一読ください。
- 関連するタグはこちら
よくあるご質問
- 土地活用・不動産経営は初心者なのですが、どのように相談をおこなえばよいでしょうか?
- 弊社HPの電話もしくはお問い合わせフォーム・資料請求フォームから、お気軽にお問い合わせください。ご要望に応じて、オンライン面談・電話・メール等での対応が可能です。
- 生和コーポレーションの土地活用・不動産経営には、どのような特徴があるのですか?
- 4大都市圏での営業に特化し、土地活用一筋50年を超えております。マンション・アパートの累計着工戸数は100,000戸を超え、都市部に強い生和だからこそ、サブリース・一括借上げの入居率98%台を実現しています。
- お問い合わせ後の流れはどのようになっているのですか?
- お問い合わせ頂いた電話番号もしくはメールアドレスに担当がご連絡致します。
お客様のご相談内容に応じて、経験・知識が豊富な担当が対応致します。
生和コーポレーション編集部
「すべてはオーナー様のために」をテーマに、土地をお持ちの方の目線で、不動産の有効活用に関連する情報を発信しています。当社の豊富な実績をもとに、税理士や建築士、宅地建物取引士などの有資格者が監修した記事も多数掲載。賃貸マンションの建設・管理から相続や税金の話まで、幅広いコンテンツを公開中。
編集部へのご意見・情報提供などございましたらお問い合わせからお願いします
他の初めてマンション建築をご検討の方へを見る

マンション建築・経営で失敗しないために知っておきたいこと
事業を転換して収入を安定させるためや、将来の相続税対策のためにマンション経営を始めようと考えたとき、どうしても頭をよぎる…

マンション建設のローンと金利の関係性について
マンションを建設するには多額の費用がかかります。自己資金だけで賄えない分は、たいていはローンを活用してマンション建築を始…

マンション建築に関わる補助金制度について
マンション経営をはじめるためには、まず賃貸物件を用意しなければなりません。しかし、マンションを新しく建築するとなると、膨…
全タグ
- 土地オーナー様のお悩み解決
-
- 土地活用に必要な資金と自分にあったローンの選び方
- 土地活用に必要な融資を受ける為の準備
- 土地活用に適した立地条件とは
- 一括借上げ(サブリース)の仕組みやリスク、良くあるトラブル事例
- 家賃保証の仕組みと良くあるトラブル
- 土地活用の種類と特徴について
- お金のかからない土地活用アイデア4選!土地はあるが自己資金がなくても始められる?
- 土地活用に必要な資金と自分にあったローンの選び方
- 賃貸併用住宅のメリット・デメリット
- 賃貸併用住宅運用によくあるトラブル
- 賃貸併用住宅を成功させるために知っておきたい失敗事例
- 知っておくべき賃貸併用住宅の危険性(リスク)
- 土地なしからの賃貸併用住宅
- 賃貸併用住宅の資産価値と評価方法
- 賃貸併用住宅をやるなら木造?鉄筋(RC)?おすすめの構造は
- サラリーマンでもできる賃貸併用住宅
- 賃貸併用住宅とは?後悔しないためのメリットやデメリット・注意点について解説
- 賃貸併用住宅は収支とシミュレーション
- 賃貸併用住宅で住宅ローン控除を受ける条件と方法
- 自己資金0円でも賃貸併用住宅を買うことはできるのか
- 賃貸併用住宅ローンの減税方法
- 賃貸併用住宅に必要な頭金の相場とは
- 賃貸併用住宅とは ~経営のための基礎知識~
- 賃貸併用住宅を経営するメリットとデメリット
- 賃貸併用住宅の知っておくべきリスクと注意点について
- 土地なしから賃貸併用住宅をはじめるには
- 賃貸併用住宅を始めるときの費用(建築費)はいくら位?
- 賃貸併用住宅の資産価値と評価方法の考え方
- 賃貸併用住宅をやるなら木造?鉄筋コンクリート造(RC造)?
- サラリーマンでも賃貸併用住宅の経営はできるのか
- 賃貸併用住宅は儲かるのか?利回りと年収の関係性
- 賃貸併用住宅の収支計画の立て方
- 狭小地でも賃貸併用住宅を建てることはできるのか?
- 賃貸併用住宅で住宅ローン控除を受ける条件と注意点
- 自己資金0円で賃貸併用住宅の経営はできるのか
- 賃貸併用住宅における住宅ローン控除の方法と必要な書類
- 賃貸併用住宅に必要な頭金の考え方
- 賃貸併用住宅の中古と新築の違い
- 賃貸併用住宅の種類
- 一戸建ての賃貸併用住宅の特徴
- 賃貸併用住宅のデザインと間取り
- 最近流行りのシェアハウスの賃貸併用住宅
- 4階建て・5階建ての賃貸併用住宅の活用方法
- 賃貸併用住宅の中古と新築のメリット・デメリット
- 一戸建ての賃貸併用住宅の特徴とは
- 賃貸併用住宅の間取りとデザインを考える
- シェアハウス賃貸併用住宅のメリット・デメリット
- 2階建て・3階建て賃貸併用住宅の間取り・特徴
- 4階建て・5階建ての賃貸併用住宅の活用事例
- 賃貸併用住宅の上手な節税・減税対策とは
- 賃貸併用住宅の確定申告の方法
- 賃貸併用住宅ローンの減税・控除について
- 賃貸併用住宅で銀行から融資してもらう為の条件とは
- 賃貸併用住宅の登記方法と流れ
- 賃貸併用住宅を区分登記するメリット・デメリット
- 賃貸併用住宅の節税対策・効果
- 賃貸併用住宅の相続税対策と固定資産税対策
- 賃貸併用住宅の住宅ローン控除とローン利息の計算方法
- 賃貸併用住宅における銀行融資の種類と違い
- 賃貸併用住宅の登記の種類と申請の流れ
- 賃貸併用住宅を区分登記する必要性と注意点
- 建物管理を委託する際の契約の流れ
- エレベーター点検に課せられている義務と頻度
- 給水設備の方式の種類と比較
- 消防設備の「総合点検」と「機器点検」の違いとは
- ビルや建物管理に必要な法定点検の重要性
- 消防設備の特例基準と特例申請の方法とは
- 底地とは?借地との違いやメリット・デメリットを解説
- 代理人をたてて土地(不動産)売却する際の注意点
- 不動産(土地)売却の流れ
- 底地の評価手法とは
- 親子・親族間での土地(不動産)売却でかかる税金について
- 土地(不動産)売却した際の控除の対象となる税金
- 住み替えによる不動産売却にかかる税金の特例とは
- 土地(不動産)売却をした際の住民税について
- 媒介契約とは?その種類や代理契約との違いを解説
- 不動産の媒介契約のメリットとは
- 遠方(遠隔地)にある土地(不動産)を売却する際の注意点
- 不動産売却の引き渡し準備と注意点
- 扶養内の妻名義を土地(不動産)売却する際の注意点とは
- 不動産管理とは?業務フローや会社の役割について解説
- 不動産投資の個人と法人の違い、法人化のタイミング、節税効果を知る
- CRE戦略とは?不動産を通して企業の価値を高める方法や事例をご紹介
- 良いサブリース会社の選び方~賃料相場や損益分岐点から比較~
- サブリース契約におけるトラブル原因や対処法、事例について解説
- サブリースは簡単に解約できない?仕組み・問題点・解約手順をご紹介
- 家賃保証とは?メリット・デメリットやサブリースとの違いも紹介
- 家賃収入にかかる税金とは。その種類と計算方法を解説
- 家賃収入・不動産所得の確定申告は必要?必要書類や書き方・申告方法を解説
- 相続の不動産登記の流れは?必要書類や費用、自分でやる場合の注意点を解説
- 相続税の節税対策に不動産投資は有効か?他の相続税対策もご紹介
- 家賃収入には消費税がかかるのか?賃貸物件の課税と非課税の違いとは
- 土地の相続税が軽減される「小規模宅地等の特例」の節税対策とは?
- 土地の相続税が払えないときの対処方法とは?延納精度や物納制度についても解説
- 家賃収入で生計を立てるやり方とは?収入を得るための流れ・仕組み
- 家賃収入の所得税はどのくらいかかるのか?税金の計算方法を説明
- 配偶者は相続税の控除あり!税制優遇の条件とは?
- 対策するなら知っておこう!相続税と路線価の関係
- 不動産にかかる相続税!どうやって計算すると得?
- 覚えておこう!相続税の基礎控除
- 農地を活用する方法、有効な土地活用について解説
- 不動産の相続手続きとは?相続の流れや相続登記の必要書類を解説!
- 不動産贈与税の税率計算方法|贈与時の注意点についても解説
- 併用住宅とは? 定義や固定資産税の影響について解説
- 不動産売却(譲渡)時にかかる譲渡所得税とは?計算方法や税金対策を解説
- 減価償却の計算方法は?定額法・定率法の違いをわかりやすく解説!
- 土地の相続税はいくらかかる?計算方法や節税のポイントを解説
- 減価償却とは?償却の計算方法や耐用年数についてわかりやすく解説
- 建物の耐用年数とは?構造別の年数一覧や減価償却費の計算方法について解説
- 不動産投資は節税できる?仕組みや注意点を解説
- 消費税還付とは?仕組みや還付の条件について
- 一括借り上げとは?契約のメリットやサブリースの違いについて解説
- 不動産の取得・保有・売却にかかる税金は?
- 家賃収入の税金はどのくらいかかるの?不動産所得の税額
- 家を売却すると税金がかかる?計算方法や控除を紹介
- 不動産投資に役立つ資格とは?メリットやおすすめ資格を紹介
- 家賃滞納による強制退去の進め方
- 無償譲渡とは?土地や不動産を無償譲渡で受けるときのメリットや注意点について解説
- 根抵当権とは?抵当権との違いや抹消手続きについて
- 空き家活用の方法9つ!具体的な事例や注意点を徹底解説
- 地価公示価格とは?実勢価格との違いや調べ方について解説
- 閉鎖謄本・登記簿とは?取得方法や利用タイミングについて解説
- 駐車場経営の固定資産税とは?いくらかかる?計算方法や節税のポイントについても解説
- 遊休地とは?活用方法や活用する際のポイントを紹介!
- 土地活用の方法9選を徹底比較!注意点や相談先の選び方を解説
- アパート経営をやめたいときはどうすれば良い?やめるタイミングや手順・費用
- アパート経営をやめて売却する方法|準備・手順・かかる費用を徹底解説
- 土地活用にはマーケティングが必要?具体的な調査項目や活用方法を解説!
- 愛知県でおすすめの土地活用4選!活用事例も紹介
- 千葉県でおすすめの土地活用方法7選!相談先の選び方も解説
- 事業用定期借地権とは?通常借地権との違いやメリット・デメリットを紹介
- 貸家建付地とは?自用地や貸宅地との違い・評価額の算出方法
- 立ち退き料の費用相場や計算方法 | アパートやマンション中心に交渉のポイントと減額のコツを紹介
- 土地活用方法・検討のポイント
-
- 土地活用にも補助金が申請できる
- 土地活用における一括借上げ(サブリース)の仕組みとは?土地活用の3つの方法を詳しく解説!
- 土地活用一括借り上げの仕組みとメリット・デメリット
- 土地活用による資産運用のメリット・デメリット
- 土地活用・不動産投資の上手な節税対策の方法
- 土地活用で減価償却を活かした節税対策
- 土地(不動産)売却の測量は必要か
- 売れる土地と売れない土地の違いは?売却までの流れも解説
- 土地を売却する方法は?売却の流れや費用・税金、注意したい土地売却のケース
- 不動産(土地)売却した際の確定申告の時期と必要書類
- 土地(不動産)売却をした際の譲渡税について
- 土地の名義変更を徹底解説|流れや必要書類、費用について
- 土地の相続放棄はできるのか?相続破棄の手続き方法やメリット・デメリットをご紹介
- 土地の相続税はいくらかかる?評価額の計算方法や節税できる控除・特例について解説
- 土地・不動産の生前贈与はすべきか?税金計算方法や費用、手続きを解説
- 土地の相続税対策とは?土地の評価方法や税金の費用について解説
- 土地相続の手続きを徹底解説!土地の分け方や名義変更の流れも
- 土地・不動産の贈与税はいくらからかかる?評価額の計算方法や節税方法
- 土地の固定資産税・都市計画税はいくら?仕組みや計算方法・節税のコツ
- 遊休地の活用方法一覧!おすすめの活用方法やメリット・デメリットも紹介
- 土地オーナー様が知っておきたい土地活用法とは?成功するために必要なこと
- 土地活用として「貸す」ときはどのようなメリット・デメリットがある?注意点も解説
- 土地活用の進め方とは?相談先や成功までの流れを解説!
- 土地活用の建築費はどれくらい?パターン別の初期費用を解説!
- 相続税対策に有効な土地活用方法5選!相続税の基本もわかりやすく解説
- 遊休地にかかる税金とは?固定資産税を抑えるための活用方法や対策
- 狭い土地の上手な活用方法は?狭小地の最適な土地活用3選
- 建替えのメリットとは?工事費用や設計についてデメリットと併せて解説
- 定期借地権とは?その種類や土地活用におけるメリット・デメリットを解説
- 土地活用可能な敷地面積は?活用方法別に必要な広さを解説
- インボイス制度とは?マンション・アパート経営への影響ととるべき対策を徹底解説
- 土地活用における等価交換とは?仕組みやメリット・注意点
- ガソリンスタンド跡地の土地活用の事例
- 事例つきで解説!駐車場からの土地活用
- 更地にすると固定資産税は高くなるのはなぜ?その理由や計算方法、安くする方法を解説
- 資材置き場の土地を活用するには?収入やメリット・デメリット、ポイントを解説
- 100坪は何平米?土地活用法や活用のポイント
- 固定資産税の計算方法は?具体的なシミュレーションと特例・減額措置
- 失敗しない土地活用
-
- 土地活用の成功例と失敗例4選!成功のためのポイントを解説
- 土地活用業界の現状とニーズ
- 土地活用の特徴・種類について
- 土地活用のアイデア20選《2025年最新》運用のメリットや進め方も解説!
- 土地活用で押さえておくべき問題点とリスクとは?少ないリスクで土地活用を行なう方法
- 土地活用における税金の仕組み
- 土地活用で成功するために押さえておくべきポイント
- 土地活用に役立つ資格「宅建」とは
- 土地活用における利回りの基本的な考え方や注意したいポイントを解説
- 土地活用は儲かる? 収入・利益を出すポイントについて
- 老後を考えた土地活用のすすめ
- 土地活用で成功するために押さえておくべきポイント
- 土地活用相談はどこにするべき?相談先の業者・専門家の選び方を解説
- 土地活用方法8種類の比較!注意点についても解説
- 土地活用のコンサルティングとは?
- 土地活用による相続税対策の仕組み
- マンション建築・経営で失敗しないために知っておきたいこと
- 土地活用で社会貢献!福祉に役立てるという選択肢
- コインパーキング経営で土地活用!メリットや成功のコツを解説
- 田舎でおすすめの土地活用アイデア3選!活用方法や注意点を解説
- 遊休地の活用|駐車場経営を成功させるには?メリット・デメリット、始め方も解説
- 土地活用でマンション経営を行なうメリット・デメリットは?
- 土地を活用せず売却しても良い?メリットやデメリットを解説
- 一括借上げ(サブリース)のメリット・デメリットは?管理委託方式との3つの比較ポイントも解説!
- 土地活用で介護施設を経営するメリット・デメリットは?流れや費用も解説!
- 商業施設とは?店舗ビルとの違いや定義について解説
- 医療施設で土地活用する場合のメリット・デメリットは?種類や立地条件も解説
- アパート経営で悩んだときは
-
- アパート経営の利回りの最低ラインは?計算方法や利回り相場を解説
- アパート経営におけるインターネット導入費用の目安と利益を出すポイント、注意点を解説
- アパート経営とマンション経営の違い
- アパート経営・賃貸マンション経営のメリットとデメリット
- アパート経営・マンション経営の家賃設定はどうやって決めるか
- アパート経営・マンション経営をはじめるポイント
- アパート経営・マンション経営における連帯保証人の必要性
- アパート経営・マンション経営を成功させるコツと基礎知識
- ローンを活用したアパート経営・マンション経営
- アパート経営・マンション経営におけるキャッシュフローの落とし穴
- アパート経営・マンション経営の管理業務とは(自主管理・委託管理)
- アパート経営・マンション経営に必要なメンテナンスとは
- アパート経営・マンション経営で大事な掃除のポイントとは
- アパート経営・マンション経営で住宅ローンを活用する方法
- アパート経営・マンション経営でローンを活用するメリット
- アパート経営・マンション経営の必要経費(維持費・管理費)
- アパートの減価償却とは?計算方法や節税方法を解説
- アパート経営・収益物件のチェックポイントは?
- アパート経営の災害リスク(地震・火事)と保険
- アパート経営・マンション経営における保険の重要性と保険の種類
- アパート経営・マンション経営の空室対策・入居率を上げる方法
- アパート経営のリスクは?10個のリスクとその対処法を解説!
- アパート経営・マンション経営の白色申告【経費・必要書類】
- アパート経営・マンション経営の年末調整の書き方
- アパート経営・マンション経営における所得税
- アパート経営・マンション経営にかかる消費税とは
- アパート経営・マンション経営における白色申告と経費の考え方
- アパート経営・マンション経営における年末調整の必要性と確定申告の方法
- アパート経営・マンション経営はサラリーマンの節税対策になり得るか
- アパート経営・マンション経営に多い騒音トラブルへの対策と解決方法
- アパート経営の税金対策・節税の方法
- アパート経営の初期費用はいくら?収益モデルについても解説
- マンション経営・アパート経営のランニングコストはいくら?相場や内訳を解説
- アパート経営の年収・収入はいくら?収入と支出の内訳やキャッシュフローを増やすコツ
- アパート経営は儲かる?キャッシュフロー例や儲かるポイントを徹底解説
- 大阪はマンション経営・アパート経営に向いている? 大阪の特徴やおすすめのエリア・東京都との違いを解説
- 東京都がマンション・アパート経営におすすめな理由|エリア・路線と経営成功のポイント
- 福岡がマンション経営・アパート経営におすすめな4つの理由
- 名古屋がマンション経営・アパート経営に適する理由は?賃貸経営に適した3つのエリアも紹介
- アパート経営の初期費用と必要な自己資金はどのくらい?収益モデルについても解説
- アパート経営方法・検討のポイント
-
- アパート経営・マンション経営のはじめ方<入門>
- アパート経営の基本を徹底解説!初期費用や儲からないと言われる理由を紹介
- アパート経営・賃貸マンション経営の仕組みと魅力
- アパート経営の利回りの最低ラインは?計算方法や利回り相場を解説
- アパート経営におけるインターネット導入費用の目安と利益を出すポイント、注意点を解説
- アパート経営・賃貸マンション経営のメリットとデメリット
- アパート経営・マンション経営における連帯保証人の必要性
- アパート経営・マンション経営を成功させるコツと基礎知識
- アパート経営・マンション経営の管理業務とは(自主管理・委託管理)
- アパート経営・マンション経営に必要なメンテナンスとは
- アパート経営・マンション経営で大事な掃除のポイントとは
- アパートの減価償却とは?計算方法や節税方法を解説
- アパート経営・収益物件のチェックポイントは?
- アパート経営(賃貸経営)のメリットとリスクとは?
- アパート経営の成功率を上げるコツとは?失敗する原因も併せて解説
- 失敗しないアパート経営
-
- アパート経営・マンション経営のはじめ方<入門>
- アパート経営の基本を徹底解説!初期費用や儲からないと言われる理由を紹介
- アパート経営・賃貸マンション経営の仕組みと魅力
- 【新築vs中古】アパート経営・マンション経営する際のメリットデメリット
- 老後の年金対策とアパート経営・賃貸マンション経営
- アパート経営・賃貸マンション経営を法人化するメリットとは
- マンション経営・アパート経営に資格は必要?求められる知識とおすすめの資格
- アパート経営・マンション経営の家賃保証契約とは
- アパート経営・マンション経営の一括借上げシステムとは
- アパート経営・マンション経営の一括借上げと家賃保証の違いとは
- 公務員がアパート経営・マンション経営をすると違法になるのか
- アパート経営・マンション経営における地方と都心の比較
- アパート経営・マンション経営は土地がなくてもスタートできる!?資金 や契約の注意点について解説
- アパート経営の新築と中古の違い
- アパート経営・マンション経営に関する相談はどこにするべきか
- アパート経営・マンション経営における個人事業主と法人の考え方
- アパート経営・マンション経営の手続きと流れ
- アパート経営・マンション経営の間取りの種類と特徴
- アパート経営・マンション経営はサラリーマンの副業でもできる
- アパート経営・マンション経営を成功させる4つのコツ
- アパート経営・マンション経営のスタートするまでの流れ
- アパート経営・マンション経営の間取りの重要性・種類
- アパート経営・マンション経営はサラリーマンの副業として成り立つか
- アパート経営・マンション経営の上手な資金調達方法
- 自己資金・頭金0円でもアパート経営・マンション経営はできるか?
- アパート経営・マンション経営に必要な経費(維持費・管理費)
- アパート経営・マンション経営の収支計画シミュレーション
- アパート経営・マンション経営で銀行から融資を受けやすくする方法
- アパート経営・マンション経営にかかる修繕費の目安とは
- アパート経営・マンション経営に必要な経費の種類とは?経費として計上できる項目とできない項目
- アパート経営・マンション経営における建替えの必要性とタイミング
- アパート経営・マンション経営においてリフォームを行うことのメリットや効果
- アパート経営・マンション経営においてリノベーションを行うことのメリットや効果
- アパート経営・マンション経営でローンの借り換えをする際の注意点
- アパート経営・マンション経営の資金調達方法
- 自己資金・頭金0円でもアパート経営・マンション経営は可能
- アパート経営・マンション経営におけるキャッシュフローの重要性と落とし穴
- アパート経営・マンション経営の収支計画を立ててみよう
- アパート経営・マンション経営で銀行融資の種類と審査ポイント
- マンション・アパート経営で失敗する理由10選 | 成功のための対策も解説
- アパート経営・マンション経営で検討したい保険の種類
- アパート経営・マンション経営で空室率が上がる原因と空室対策
- アパート経営・マンション経営で失敗しないためには
- アパート経営・マンション経営の相続税対策
- アパート経営・マンション経営の青色申告【経費・必要書類】
- サラリーマンがマンション・アパート経営する時の税金と節税対策
- アパート経営・マンション経営の確定申告に必要な基礎知識
- アパート経営・マンション経営に税務調査対策は必要か
- アパート経営・マンション経営における節税対策の効果と仕組み
- アパート経営・マンション経営による相続税対策
- アパート経営・マンション経営における青色申告と経費の考え方
- アパート経営・マンション経営における経費の範囲と節税のポイント
- マンション経営で悩んだときは
-
- マンション経営に必要な初期費用とは?相場や内訳を解説
- アパート経営とマンション経営の違い
- マンション経営を始めるのに自己資金は必要なのか
- アパート経営・賃貸マンション経営のメリットとデメリット
- アパート経営・マンション経営の家賃設定はどうやって決めるか
- アパート経営・マンション経営をはじめるポイント
- アパート経営・マンション経営における連帯保証人の必要性
- アパート経営・マンション経営を成功させるコツと基礎知識
- ローンを活用したアパート経営・マンション経営
- マンション経営の減価償却費の計算方法と活用方法
- アパート経営・マンション経営におけるキャッシュフローの落とし穴
- アパート経営・マンション経営の管理業務とは(自主管理・委託管理)
- アパート経営・マンション経営に必要なメンテナンスとは
- アパート経営・マンション経営で大事な掃除のポイントとは
- アパート経営・マンション経営で住宅ローンを活用する方法
- アパート経営・マンション経営でローンを活用するメリット
- アパート経営・マンション経営の必要経費(維持費・管理費)
- アパート経営・マンション経営における保険の重要性と保険の種類
- アパート経営・マンション経営の空室対策・入居率を上げる方法
- アパート経営・マンション経営の白色申告【経費・必要書類】
- アパート経営・マンション経営の年末調整の書き方
- アパート経営・マンション経営における所得税
- アパート経営・マンション経営にかかる消費税とは
- アパート経営・マンション経営における白色申告と経費の考え方
- アパート経営・マンション経営における年末調整の必要性と確定申告の方法
- アパート経営・マンション経営はサラリーマンの節税対策になり得るか
- マンション経営の騒音トラブルを起こさないための対策
- アパート経営・マンション経営に多い騒音トラブルへの対策と解決方法
- マンション経営は儲かるって本当?仕組みや収益を得る方法を徹底解説
- マンション経営・アパート経営のランニングコストはいくら?相場や内訳を解説
- 一棟マンション経営にかかる初期費用・維持費用はいくら?相場や成功するためのポイント
- 大阪はマンション経営・アパート経営に向いている? 大阪の特徴やおすすめのエリア・東京都との違いを解説
- 東京都がマンション・アパート経営におすすめな理由|エリア・路線と経営成功のポイント
- 福岡がマンション経営・アパート経営におすすめな4つの理由
- 名古屋がマンション経営・アパート経営に適する理由は?賃貸経営に適した3つのエリアも紹介
- マンション経営方法・検討のポイント
-
- アパート経営・マンション経営のはじめ方<入門>
- アパート経営・賃貸マンション経営の仕組みと魅力
- 【初心者向け】マンション経営のメリット・デメリット、初期費用や成功するポイントを解説
- アパート経営・賃貸マンション経営のメリットとデメリット
- アパート経営・マンション経営における連帯保証人の必要性
- アパート経営・マンション経営を成功させるコツと基礎知識
- アパート経営・マンション経営の管理業務とは(自主管理・委託管理)
- アパート経営・マンション経営に必要なメンテナンスとは
- アパート経営・マンション経営で大事な掃除のポイントとは
- マンション経営で欠かせない地震保険と火災保険
- マンション経営の仕組みとは?メリットとリスクも解説!
- 失敗しないマンション経営
-
- アパート経営・マンション経営のはじめ方<入門>
- アパート経営・賃貸マンション経営の仕組みと魅力
- 【初心者向け】マンション経営のメリット・デメリット、初期費用や成功するポイントを解説
- 【新築vs中古】アパート経営・マンション経営する際のメリットデメリット
- 老後の年金対策とアパート経営・賃貸マンション経営
- マンション経営をするのに自己資金は必要なのか
- アパート経営・賃貸マンション経営を法人化するメリットとは
- マンション経営・アパート経営に資格は必要?求められる知識とおすすめの資格
- アパート経営・マンション経営の家賃保証契約とは
- アパート経営・マンション経営の一括借上げシステムとは
- アパート経営・マンション経営の一括借上げと家賃保証の違いとは
- 公務員がアパート経営・マンション経営をすると違法になるのか
- アパート経営・マンション経営における地方と都心の比較
- アパート経営・マンション経営は土地がなくてもスタートできる!?資金 や契約の注意点について解説
- アパート経営・マンション経営に関する相談はどこにするべきか
- アパート経営・マンション経営における個人事業主と法人の考え方
- アパート経営・マンション経営の手続きと流れ
- アパート経営・マンション経営の間取りの種類と特徴
- アパート経営・マンション経営はサラリーマンの副業でもできる
- アパート経営・マンション経営を成功させる4つのコツ
- アパート経営・マンション経営のスタートするまでの流れ
- アパート経営・マンション経営の間取りの重要性・種類
- アパート経営・マンション経営はサラリーマンの副業として成り立つか
- アパート経営・マンション経営の上手な資金調達方法
- 自己資金・頭金0円でもアパート経営・マンション経営はできるか?
- アパート経営・マンション経営に必要な経費(維持費・管理費)
- アパート経営・マンション経営の収支計画シミュレーション
- アパート経営・マンション経営で銀行から融資を受けやすくする方法
- アパート経営・マンション経営にかかる修繕費の目安とは
- アパート経営・マンション経営に必要な経費の種類とは?経費として計上できる項目とできない項目
- アパート経営・マンション経営における建替えの必要性とタイミング
- アパート経営・マンション経営においてリフォームを行うことのメリットや効果
- アパート経営・マンション経営においてリノベーションを行うことのメリットや効果
- アパート経営・マンション経営でローンの借り換えをする際の注意点
- アパート経営・マンション経営の資金調達方法
- 自己資金・頭金0円でもアパート経営・マンション経営は可能
- アパート経営・マンション経営におけるキャッシュフローの重要性と落とし穴
- アパート経営・マンション経営の収支計画を立ててみよう
- アパート経営・マンション経営で銀行融資の種類と審査ポイント
- マンション・アパート経営で失敗する理由10選 | 成功のための対策も解説
- アパート経営・マンション経営で検討したい保険の種類
- アパート経営・マンション経営で空室率が上がる原因と空室対策
- アパート経営・マンション経営で失敗しないためには
- マンション経営の節税の仕組みと効果・経費計上する際のポイントについても解説
- アパート経営・マンション経営の相続税対策
- アパート経営・マンション経営の青色申告【経費・必要書類】
- サラリーマンがマンション・アパート経営する時の税金と節税対策
- アパート経営・マンション経営の確定申告に必要な基礎知識
- マンション経営の固定資産税はいくらかかる?計算方法や減税措置について
- アパート経営・マンション経営に税務調査対策は必要か
- アパート経営・マンション経営における節税対策の効果と仕組み
- アパート経営・マンション経営による相続税対策
- アパート経営・マンション経営における青色申告と経費の考え方
- アパート経営・マンション経営における経費の範囲と節税のポイント
- マンション経営の赤字を回避するには?収支が悪化する原因と対策















