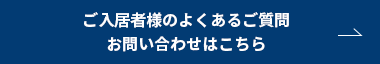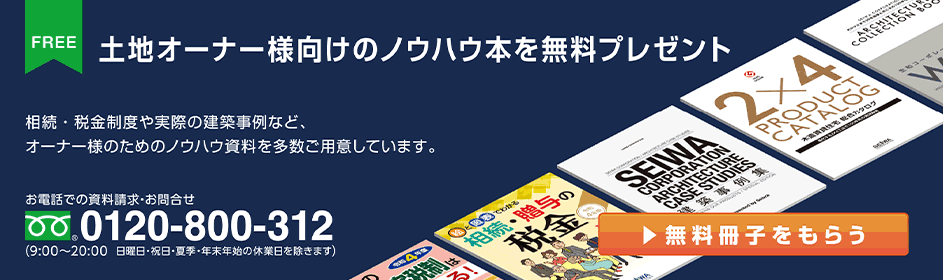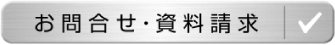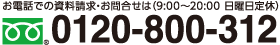賃貸併用住宅を建設するオーナーさんの多くは、その成功を夢見ていることと思いますが、現実はそれほど甘くはありません。
失敗することもありますしそれから学ぶことも多くありますので、失敗事例を知りそこから教訓を学ぶことでより成功に近づけるのです。
賃貸併用住宅の失敗事例
魅力ある物件作りに失敗してしまう
賃貸併用住宅を建設するにあたり、オーナーである自分たちの居住空間の快適性ばかりを追求し、入居者の利便性や快適性を考えずに住宅建設をしたことが失敗につながった事例もあります。
ずっとその住宅で快適に暮らすのはオーナーである自分たち家族ですから、自分たちの利便性を優先して考えてしまいがちになりますが、それを優先したことで賃貸空間の利便性や快適性が失われてしまっては、物件としての魅力がなくなってしまうのです。
修繕費の準備不足
賃貸併用住宅で収入が得られるのは入居者が入っていてくれるからであり、それがいなくなってしまえば収入自体が途絶えてしまいます。
家賃収入が途絶えてしまうことで家計に与える影響も大きいですから、できる限り絶え間なく入居者に入ってもらうことが、賃貸併用住宅経営成功のコツだと言えます。
住宅を建設した当初は物件自体が新しいため、入居者やこれから入居を考えている方にとっても魅力的な物件なのですが、年数の経過共にさまざまな箇所に傷みや汚れ、劣化が見られるようになります。
それが目立つようになると物件自体の魅力が失われてしまうため、入居者が集まりにくくなるのです。
その状況を改善するためにリフォームを行うのですが、その費用まで考えが及ばないオーナーさんもいらっしゃいます。
リフォームにかかる費用のことを建設当初から考えていなければ、その費用が調達できずいつまでも物件の価値は低いままで、入居者が集まらなくなってしまうのです。
相続対策は万全に
賃貸併用住宅を相続対策として建設される方もいらっしゃいますが、その場合は相続の対象がご家族全員となるため、それ所以のトラブルが起こりやすいのです。
例えば家賃の金額を変える、リフォームする、解体するといった作業にも、相続対象となる家族全員の同意が必要となるため、意見がまとまらないのです。
相続対策として物件を残す場合は、その経営について遺書などにきちんと明記しておくことで、家族同士の無用なトラブルを回避できるようになります。
関連ページ:失敗しない為の土地活用とその目的とは
土地活用のご相談、まずはお気軽に。相談から物件管理まで一貫したサポートを提供。
賃貸併用住宅経営を成功させるために(失敗しないために)
経営の目的を明確にする
賃貸併用住宅を経営する目的を明確にすることが、経営を成功に導くスタートポイントです。具体的には賃貸併用住宅の経営における目的とはどういうものでしょうか?
たとえば家賃収入を自宅建築資金のための住宅ローンの返済に充てるのか、趣味や生活費の一部に充てるのか、ローン完済後の安定収入として充てるのか、土地を有効活用して固定資産税を削減するかなど目的を明確にすることです。
また目標にする家賃収入を得るためには、どのような間取りで何戸を賃貸スペースとして設けるのかなど、賃貸併用住宅の規模、住宅ローンの借入金額、返済期間、目指す利回りなどを数値化することが大切です。しかし、高い利回りを追い求めすぎたことで、建物の管理を怠り、結果として空室が増えたことで資金繰りが困難になってしまったという失敗に繋がりかねませんので、注意しましょう。さらに、賃貸併用住宅を相続対策のために入手する場合、運営方針を事前に話し合っておくなどしておくとスムーズに相続を執り行うことが可能になります。
以上のように目的によって事業計画も変わるため、安定収入の確保、節税対策、相続・贈与対策なのかはっきりさせることが重要です。
徹底的に市場調査を行い、事業計画を立てる
市場調査を怠ると、空室リスクが高まり、思ったように家賃収入が得られないなど失敗に繋がるケースが多くあります。そのためにも建築する周辺の家賃相場、間取りなどを綿密に調査して、どのような入居者のニーズがあるのかを十分に検討する必要があります。
例えば、大学が多く集まる街にファミリータイプの物件を建てるよりも、一人暮らし向けのワンルームタイプのニーズのほうが高いと想定できます。もし保育園や公園、公共施設が近くにある場合など、子育て世代のニーズが高いとされるエリアであれば、ファミリー向けの間取りを作るなど、入居者目線で賃貸スペースをつくることが重要です。
また、賃貸併用住宅はオーナー自身も居住する物件です。設備や間取りをオーナーの意向ばかり反映すると、入居者のニーズに合わないことが考えられるため、管理形態を含め入居者にとって魅力ある物件にすることを念頭に置くようにしましょう。
賃貸併用住宅も立派な賃貸ビジネスなので、目標をしっかり掲げ、どれくらいの事業規模(戸数・家賃収入)で建物を建てるのかなどを十分に検討し、建設時期、部屋数、間取りなどの構造を考えながら事業計画を立てていく必要があります。事業計画の立案には、不動産会社をはじめとするプロの知見も取り入れながら、住宅ローンでの資金調達を含め収支計画の内容を盛り込みます。さらに、空室リスク・金利の変動・修繕費・家賃の変動など、さまざまなリスク要因があることを忘れてはいけません。リスクに直面した時に経営難に陥らないためにも、どのような対応できるのかを判断する知識を養っておくことが大切です。
信頼できる不動産会社・不動産管理会社を選ぶ
不動産経営を失敗させないためにも、パートナーとなる不動産会社・不動産管理会社選びも重要です。一からオーナーが市場調査をするのは、調査のポイントや方法がわからず非効率と言えるでしょう。そのためにも、どのような規模で何を目的に経営していきたいのかを不動産会社に伝え、市場調査、建築プラン、収支計画、将来の空室リスクに備えるための一括借上げなど、運用の効率化と安定した家賃収入を得るためのノウハウをアドバイスしてもらえるパートナー探しが重要とされます。
また、建築後の運用管理業務は不動産管理会社に委託することで、日々の清掃業務だけでなく入居者様の対応業務も担当してもらえるため、安心して賃貸併用住宅経営に専念できるでしょう。
しかし、賃貸併用住宅の経営を失敗させないためには、不動産管理会社に任せっきりにするのではなく、オーナー様も経営に携わる姿勢が必要と言えます。賃貸併用住宅経営を成功させるためのポイントをしっかり押さえて、長期的に安定した経営を成功させましょう。
- 関連するタグはこちら
よくあるご質問
- 土地活用・不動産経営は初心者なのですが、どのように相談をおこなえばよいでしょうか?
- 弊社HPの電話もしくはお問い合わせフォーム・資料請求フォームから、お気軽にお問い合わせください。ご要望に応じて、オンライン面談・電話・メール等での対応が可能です。
- 生和コーポレーションの土地活用・不動産経営には、どのような特徴があるのですか?
- 4大都市圏での営業に特化し、土地活用一筋50年を超えております。マンション・アパートの累計着工戸数は100,000戸を超え、都市部に強い生和だからこそ、サブリース・一括借上げの入居率98%台を実現しています。
- お問い合わせ後の流れはどのようになっているのですか?
- お問い合わせ頂いた電話番号もしくはメールアドレスに担当がご連絡致します。
お客様のご相談内容に応じて、経験・知識が豊富な担当が対応致します。
他の「土地オーナー様のお悩み解決」の記事を見る
-
 土地活用において、神奈川県はとても魅力的な場所です。利用できる土地があれば、ぜひ有効に活用したいところです。それでは、どのような形で活用するのが最適なのでしょうか。 まず考えておきたいのは、神奈川県は…
土地活用において、神奈川県はとても魅力的な場所です。利用できる土地があれば、ぜひ有効に活用したいところです。それでは、どのような形で活用するのが最適なのでしょうか。 まず考えておきたいのは、神奈川県は… -
 土地所有者が自身の土地に建物を建設し、その建物を貸家として提供する場合の敷地を、貸家建付地と呼びます。貸家建付地には税額評価の際、自用地よりも評価額が低くなるという特徴があります。 本記事では、貸家建…
土地所有者が自身の土地に建物を建設し、その建物を貸家として提供する場合の敷地を、貸家建付地と呼びます。貸家建付地には税額評価の際、自用地よりも評価額が低くなるという特徴があります。 本記事では、貸家建… -
 土地の有効活用方法のなかには、「事業用定期借地権」を利用した借地事業があります。事業用定期借地権とは、あらかじめ期間を定め、事業目的で土地を貸し借りする権利のことです。 この記事では、事業用定期借地権…
土地の有効活用方法のなかには、「事業用定期借地権」を利用した借地事業があります。事業用定期借地権とは、あらかじめ期間を定め、事業目的で土地を貸し借りする権利のことです。 この記事では、事業用定期借地権… -
 千葉県に土地を所有していて土地活用を検討しているものの、どのような方法を選択すれば良いかお悩みの方もいるのではないでしょうか。 土地活用は、その土地がある場所や条件によって適する方法が異なります。また…
千葉県に土地を所有していて土地活用を検討しているものの、どのような方法を選択すれば良いかお悩みの方もいるのではないでしょうか。 土地活用は、その土地がある場所や条件によって適する方法が異なります。また… -
 愛知県で土地活用を検討しているオーナー様のなかには、「愛知県でおすすめの土地活用法は?」「土地活用する際に気をつけるポイントは?」などの疑問を持つ方もいるかもしれません。 愛知県で土地活用をするなら、…
愛知県で土地活用を検討しているオーナー様のなかには、「愛知県でおすすめの土地活用法は?」「土地活用する際に気をつけるポイントは?」などの疑問を持つ方もいるかもしれません。 愛知県で土地活用をするなら、…